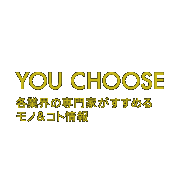- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
1月28日に出会った虫達2012.01.30
「ずいぶん変わったカメラですね!何を撮っているんですか?」
「虫を撮っています」
「こんなに寒いのに虫なんか居るんですか?」
「ほら、そこの枝にイラガの繭とその隣にはモズのハヤニエがありますよ」
「何処ですか?えっ!こんな処に居たんですね!これは面白い!」
この日は自宅から車で30分程の処にある「野山北公園」へ来ていた。
2時間程の撮影中に3人に声をかけられ、交わした言葉である。
1月28日に出会った虫達(右上から時計回りに)
モズのハヤニエ(ツチイナゴ)、ジャコウアゲハ蛹、オオムラサキの幼虫、ウラゴマダラシジミの卵(イボタノキ)、ジャコ ウアゲハ蛹、イラガの繭
イラガの繭
別名、「雀の小便ダコ」。
天秤棒で担ぐ桶(おけ)のことで、「たご」がなまって「ダコ」。
この写真ではまだガが出ていないので桶に見えない。幼虫は前回の(なめたらあかんぜよ!イラガ)では触ると感電したような痛みがあるので、「電気虫」とも呼ばれる。
モズのハヤニエ
モズは捕らえた獲物を樹の枝などに突き刺したりする行動を「モズのハヤニエ(早贄)」と呼ぶ。
写真の犠牲者はツチイナゴである。
ジャコウアゲハの蛹
別名「お菊虫」と呼ばれる。
怪談「皿屋敷」のお菊の後ろ手に縛られた姿に似ているので「お菊虫」。
ウマノスズクサの毒で武装して鳥などの外敵から身を守っている、ベーツ擬態である。
よく見るとオレンジ色の所が濡れた唇のようにも見えて「1枚〜2枚〜・・・」と数えているような。ゾクッ
オオムラサキの幼虫
残雪をかき分け、葉っぱを一枚一枚めくって行くと角が4対のオオムラサキの幼虫が見つかった(角が3対ならばゴマダラチョウ)。
無事にこの冬を乗り越えられるか。
2010年1月15日の「落ち葉の中の妖精」についで2階目の登場。
葉っぱの布団を丁寧にかけてここを後にする。
ウラゴマダラシジミの卵
ウラゴマダラシジミを探すには(イボタノキ)を探す。
落葉低木で高さは2mほど(写真は1mほど)。
黒い果実がこの時期でも残っているので探し易い。
卵の大きさは約1㎜、小枝の分岐部などに1〜10個ほど産みつけられる。
卵で越冬するミドリシジミ科の仲間。
蝶の愛好家の間ではゼフィルス、略してゼフと呼んでいる。
ゼフィルス (zephyrus)とは、ギリシャ語のzephyros西風の意味である。
この時の撮影技法(冬の虫を探す)
食樹を丹念に観察。樹の皮を剥ぐ(テントウ虫、コバチ、ゾウムシなど)。倒木をひっくり返す(スズメバチの女王、カブトムシの幼虫、アリなど)葉裏(グンバイ、コバチ、キジラミなど)、木柵:手すり磨き(フユシャク、アリ、コミミズクなど)
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Nikon D300、AF Micro NIKKOR 60mm 1:2.8、AF Micro NIKKOR 28-100mm 1:3.5-5.6G前玉ハズシ改造(ウラゴマダラシジミ)。ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11、SPEEDOLIHT SB-600(ウラゴマダラシジミ)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
なめたらあかんぜよ!(イラガ)2011.12.19
「サクラの幹にイラガがいるよ」と虫仲間が手招き。
1ミリ程のコバチの仲間を撮影中であったが、危険な虫は大好きなので、おっとりカメラで駆けつける。
正面からお顔を拝見したら、可愛い面をしているのだが・・・、うかつに手を出そうもんなら「なめたらあかんぜよ!」と鬼龍院花子の啖呵ならぬ毒針が刺さるので注意が必要だ。
それにしても、オレンジ色の棘(警戒色か?)のワンポイントの凄みが効いていて素敵だ。
カシャリ!
ヒロヘリアオイラガ(広縁青毒棘蛾)チョウ目イラガ科
中国からインドが原産の外来種。
幼虫の棘には毒があり、知らずに触るとハチに刺されたような痛みで飛び上がるほどで、皮膚炎を発症する恐れあり。
植樹はサクラ、ケヤキ、カキノキ、クスノキ、カシ、イタヤカエデなど。
蛹で越冬して、幼虫は6〜10月頃見られ、成虫は年2回発生する。
イラガ類は日本に27種が生息している。
繭はウズラの卵の形に似ているが大きさは1/4ほど小さい「スズメの小便ダコ」とも呼ばれる。
この個体(終齢幼虫)の大きさは20mmほどで、12月の寒空、サクラの幹にいた。
この時の撮影技法(コントラスト)
コントラストは質感表現には欠かせないアイテムです。
コントラストとは黒から白への幅の許容範囲の事を言う。
コントラストを下げると、画像の諧調(グラデーション)はなだらかになるが、下げすぎるとぼやけた印象を与える。
逆にコントラストを上げると画像のグラデーションは失われてしまうがクッキリとした印象が得られる。
棘のチクチク感を表現するためには、少しコントラストを効かせ尖鋭感を強調することが重要と考えコントラストを上げる。
すると、チクチクして触ると痛そうに見えてきるので不思議だ。
ただし、コントラストを効かせ過ぎると、暗部が潰れてしまうので、ほどほどの調整が肝心だ。
今回はPhotoshopCS5でコントラストを+65ほど効かせてシャープネスも強めにかけてみた。
カメラ設定
絞り値:F/16、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:200、露出モード:マニュアル、露出補正:なし、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離60mm
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Nikon D300、AF Micro NIKKOR 60mm 1:2.8、 ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
桜島噴火2011.10.13
2011年10月09日19時03分。昭和火口から「ドドーン」と、上空1600メートル(海抜7900FT)真っ赤に溶けた溶岩が、月明かりの夜空にはじけ散る!そのド迫力の前には誰しもが畏敬の念に打たれるのだ。
まさに生きている山なのである。
その、噴煙が長年に降り積もりシラス台地を形成したのである。
1年程前に土の取材でギネス記録保持者(桜島大根)の生産者の方を取材をしたことがある。
なぜ桜島大根はこんなに大きくなるのか?
と、問うと「ひとつには、シラス台地にゃ小さい軽石が多く混ざっとるから、そいが適度な水分を蓄えるんですわ、水分調整を自然にやっくるっからおっぜよかっとです。手間ひまかけっせえ、姿勢の良いものを選別しもす。ほいで、桜島大根と土との相性がおっぜよかったせいじゃんそか、ギネス記録の桜島大根ができもした」と優しい眼差しで話して下さった。
桜島の降灰は辛いけど地球の営みは、少しだけ恵みも分け与えてくれるのである。
今年753回目の噴火であった。
桜島(さくらじま)
鹿児島県の錦江湾(正式には鹿児島湾)にある東西約12km、南北約10km、周囲約55km、面積約77km²におよぶ火山島。かつては文字通り島であったが1914の大噴火により大隅半島と陸続きとなった。
最近活発化してきており。爆発的噴火は2009年548回、2010年は観測最多の896回であつた。
桜島の名称。
1334年頃の記録では「向嶋」と呼ばれていたが、桜島の名称が記録に現れたのは1476年以降といわれる。
その後暫くは「向嶋」と「桜島」の名称が併存していたが、1698年薩摩藩の通達により桜島に統一される。
桜島の名称の由来。3諸説がある。
1、島内に木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)を祭る神社が在ったので島を咲耶島と呼んでいたが、いつしか転訛して桜島となった。『麑藩名勝考』
2、10世紀中頃に大隅守を勤めた桜島忠信の名に由来するという説。『麑藩名勝考』
3、海面に一葉の桜の花が浮かんで桜島ができたという伝説に由来する。『麑藩名勝考』
※ウィキペディア(桜島)より引用
この時の撮影技法(カメラセッティングとシャッターチャンス)
桜島、この日は、ここ2日程大きな噴火をしていないので期待が持てるのでは?
と、黒神地区の撮影ポイントに陣取った。先ず三脚を立て、5DM2に70〜200mmF2.8を装着。
ISO400,絞りF8、シャッタースピード30秒にセット。
明るいうちに構図を決め、フォーカスリングが動かないようにテープで固定する。
レリーズと水準器を取り付けで準備は完了です。
勿論、マニアルフォーカスでISは切っておく。だいたい花火の撮影方法と同じようなセッティングである。
風向きにより、降灰からカメラを守る為にビニール袋などでレンズを覆う準備も必要です。
今回は風向きも良く必要なかった。さて、準備が整ったらいよいよその瞬間を待つのみです。
ここで重要ポイント、カメラから決して離れない事です。
シャッターチャンスはほんの一瞬!音が鳴ってからではもう遅いのです。
ただただ、爆発の瞬間をしっかりと自分の目で捉えなければシャッターチャンスを逃す事になります。
この日は運あって、まだおいどんが元気な時間帯19時に噴火してくれもした。
故郷
鹿児島は私の故郷で、子供の頃から桜島の爆発が身近にありました。
今回は姪の結婚式で帰省したので、ちょっくら撮影をさせてもらいました。
久し振りの噴火に子供の頃を思い出しながらシャッターを押しておりました。
カメラ設定
画質モード:ROW+L、色空間Adobe RGB,絞り値:F/8、シャッタースピード:30秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:0、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、ノイズ低減OFF,焦点距離120mm,ビット数16
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Canon 5D MarkⅡ、EF70-200mm F2.8L IS USM,三脚使用、レリーズ、水準器、ピントリング固定用にテープ使用。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ツクツクボウシとアブラゼミのオシッコ比べ2011.09.20
抜き足、差し足、忍び足。「エィツ!」と網を振り下ろす。
セミもさるもので、悪ガキをあざけるように「ピュッ!」と顔にシロップのオシッコをかけられて逃げられちゃった。
そんな、ほろ苦い遠い夏の日の思い出。
そういえば、都心でもセミの鳴き声がめっきり少なくなって来た今日近頃である。
そんな事を耳で感じつつ、カメラ片手に虫探しである。すると♪「ツクツクツクボーシ!ツクツクボーシ!」と、初秋の主役のひとつツクツクボウシが盛んに歌っている。
♪歌声のする方に目をやると盛んにオシッコを飛ばしているのを発見。
それも、♂犬のマーキング時とそっくりで、横の方角へ勢い良く飛ばしている。
「へ〜っ!?」アブラゼミの個体はどれも真下に「ピュッ!」なのに、このツクツクボウシは横である。
という事は、それぞれの個体または雌雄で違うのであろうか?それとも種で違うというのか?
※セミの歌声に脳みそを引っ掻きまわされ、執筆に集中できなかったファーブル先生は「セミが音に敏感か?」と、村役場の砲手に火薬を一杯つめた大砲をぶっ放してもらったが、セミは大砲の音にもちっとも驚かず歌い続けた。
このオーケストラのしつっこさはどうにもならなかった。
『おまえのシンバルに清音器をつけて、おまえのアルペジオをゆるめてはくれないか』と悩まされたけれど、さすがに、オシッコの方角までは調べておられないようだ。
※引用『ファーブル昆虫記』平岡昇訳
ツクツクボウシ(カメムシ目、ヨコバイ亜科、セミ科)
晩夏から初秋に多く見られるセミ。
体長30㎜ほど。頭部と全胸部は緑色。鳴き声は特徴的で「ジ〜、ツクツクツクボーシ、ツクツクボーシ」と十数回繰り返し「ウイヨー」最後に「ジー」と鳴き終える。警戒心が強い。
アブラゼミ(カメムシ目、ヨコバイ亜科、セミ科)
成虫は7〜9月上旬くらいまで多く見られる。
アブラゼミは世界でも珍しい翅全体が不透明のセミで、
日本の夏を象徴するセミの一種。体長は56〜60mm。
名前の由来は、油で揚げるような鳴き声から。
この時の撮影技法(タイムラグ)
オシッコの瞬間に今だ!とシャッターを押しても、タイムラグがありなかなかその瞬間は写し止められない。
そこで、何秒間隔でオシッコをするのか数えてみる。
ツクツクボウシは約20秒間隔、アブラゼミは約12秒間隔であった。
そこで、画質設定を普段のROW設定から,より連写が可能なJPGに設定変更。
それぞれのセミのオシッコの間隔をカウントしながらツクツクボウシは19秒で連写開始。
アブラゼミは11秒から連写開始を行ってタイムラグを埋める事に成功したのが上の写真である。
このように、人間の力では埋めきれないタイムラグ克服には連写が特におすすめです。
カメラ設定
「ツクツクボウシ」画質モード:JPG、色空間Adobe RGB,絞り値:F/5.6、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:太陽光、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離105mm 35mm換算レンズ焦点距離157mm,ビット数8
「アブラゼミ」画質モード:JPG、色空間Adobe RGB,絞り値:F/13、シャッタースピード:1/250秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:−0.5、ホワイトバランス:太陽光、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、内蔵スロトボON,焦点距離220mm ,35mm換算レンズ焦点距離330mm,ビット数8
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
「ツクツクボウシ」Nikon D300、AF-S Micro NIKKOR 105mm 1:2.8 ED、三脚使用
「アブラゼミ」Nikon D90、 AF-S NIKKOR VR 70〜300 1:4.5-5.6G ED
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
オオセイボウ(招かざる客)2011.09.09
9月の上旬、メタリックブルーに輝くオオセイボウが産卵を始めた。
これは自分の卵をスズバチの巣に産みつけて、スズバチに寄生するためである。
オオセイボウに見つかってしまっては万事休。
それは、自分の子供とその子供の為の餌(アオムシなど)もオオセイボウの幼虫にすべて食べられて、自分の子孫を残せなくなってしまう事を意味します。
その事を、スズバチのお母さんは知っているのか産卵後も巣の近くにいて定期的にパトロールを行います。
でも、敵もさるもの、チョットしたスキに素早く巣に穴をあけ、おしりを差し込みさっさと産卵をすませてしまいます(写真のシーン)。
それに気づいたお母さんは猛然と体当たりをして、この招かざる客を追っ払います。
悲しいかな、すでに産卵されてしまったとも知らずに?スズバチは開けられた穴を直ぐさま埋め戻して修復しますが、オオセイボウはとても執念深く、追い払われてもすぐ近くで巣の様子をうかがっているようで、観察の間4回程産卵に成功したようです。
けれどこの4回とも同じ個体かは不明である。
オオセイボウ(大青蜂)
Stibum cyanurum pacificum.セイボウ科。
体長12〜20㎜の大型のセイボウ。6〜10月に見られる。
分布は本州・四国・九勝・沖縄。光沢があり、頭部と胸部は緑色、胸部背面と腹部第2節背面は藍色。
体の表面は無数の凹凸があり、この事が光学現象で奇麗な輝きを見せるのである(構造色)。
エントツドロバチやスズバチなどに寄生する。
この時の撮影技法(撮影ポジションを考察する)
物事を第三者に解りやすく説明するには、撮影ポジションが重要と言うお話です。
今回は産卵が主要テーマなので産卵を行っているシーンを誰にでも解る画でなければ、それは失敗写真といえるでしょう。
そのような考えから、お腹が巣の中に差し込まれている場面が良く解るアングルでなければいけません。
そこで、今回はオオセイボウの動きに合わせてベストポジションを頻繁に変えて撮影しました。
被写界深度が必要な為F16まで絞り込み、シャッタースピードは比較的遅いS1/60、その訳は背景のグリーンとブルー(オオセイボウと同系色)を出す為に背景に合わせて設定しました。
カメラ設定
画質モード:ROW+F、色空間Adobe RGB,絞り値:F/16、シャッタースピード:1/60秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:-0.5、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離85mm 35mm換算レンズ焦点距離127mm,ビット数16
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Nikon D300、AF-S Micro NIKKOR 85mm 1:3.5G ED、 ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家