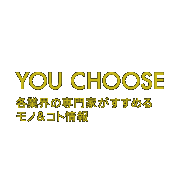- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
三春の滝桜2010.06.21
5月初旬、花見客の少なくなった頃合いを見計らい、平安時代から今日まで想像を絶するほどの多くの人々に愛でられてきた巨樹「三春の滝桜」に会いに旅に出た。
幻想とデジタルカメラを手に滝桜の前に立つ。
今年は寒気がしばらく居座っていたせいか妖艶な花もいまだ少しだけ居残って、ファインダー越しに残り少なくなった花びらが、薫風のリードで悲しげに舞っていた。
三春の滝桜とは
種類:エドヒガン系のベニシダレザクラ(紅枝垂桜)(バラ目バラ科)国天然記念物。
古くから「滝桜」と呼ばれる巨樹で、花が滝のように流れ落ちる様が見事でその呼び名になったといわれる。
また、桜の中では最も長寿な品種の一つで樹齢1000年以上ともいわれる。
樹高13.5m、幹周り8.1m(地上高1.2m)、根回りは11.3m、枝張りは幹から北へ5.5m、東へ11.0m、南へ14.5m、西へ14.0m。(三春町のホームページ参照)
場所:福島県田村郡三春町大字滝字桜久保
ちなみに、日本三大桜とは「根尾谷淡墨桜」「山高神代桜」「三春の滝桜」。
その中でも最後に妖艶な花を咲かせるのは「三春の滝桜」である。
この時の撮影技法(モノクロームの味わい)
満開の見頃ではないけれど、桜吹雪後の滝桜もまた捨てがたい魅力があるのではと、あえて時期をずらし「三春の滝桜」を撮影した。
遠くから眺め、そして徐々に巨樹に近づいて眺める。
おおよそ大人5人程で囲めるほどのねじれた根回り、四方に張り出した見事な枝張。
その迫力はまるで瀑布の裏側に迷い込んだようだ。
そんな幻想を17ミリ広角レンズのパースペクティブ(遠近法)を活用して撮影した。
モノクロームの滑らかなグラデーションと鮮烈なコントラスト、そこに潜む記憶色。
見る者に委ねる幻想の色や歴史感。
そこにこそモノクロームの深い味わいが隠されているのかもしれませんね。
NikonFとモノクロフィルムの想い出
写真を本格的に習い始めた大学生の頃、最初に買ったカメラは「NikonF」だった。
不思議だが、今でも鮮烈に蘇るのはその時の新品カメラの臭いである。
その良い臭いのするNikon Fに装填したフイルムはいつも決まってKodakのモノクロフイルム「TRI-X(現:400TX)」だった。
100フィート巻きの缶入りを買いもとめ、現像所でゴミとなった空のパトローネを貰い自分で巻き込んで使っていた。
然り、Tri-Xフイルムの臭いもまた私にはたまらなく良い臭いで、いつもカメラを手元に置いてキャパやブレッソンなどの写真集に見入っていた。
そんな学生時代、『IMAGES OF WAR』のある一枚の写真について「カラーかモノクロ」か?明け方まで熱く論争した。
それはロバート・キャパのモノクロ写真で若い兵士が銃弾に倒れ、床に血が水たまりのように広がっている凄惨な一枚だった。
「カラーでは生々過ぎるのではないか」「いや戦争の凄惨を伝えるには生々しいカラーの方が・・・」という論争であった。
1954年5月25日インドシナ。ロバート・キャパ最期の日、ライフ誌の依頼でカラーとモノクロフィルムで撮影していた。
カメラはコンタックスⅡとNikonS。
そして・・・地雷を踏んだ時に手にしていたのは、彼がもっとも信頼していた「NikonS」だといわれている。
カメラ設定
露出設定マニュアル露出、シャッタースピード1/500秒,絞りF10、ISO200
使用機材
Canon 5D MarkⅡ、17~40ミリF4( 17ミリ付近で使用)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
アオゲラ2010.06.04
染井吉野と入れ替わるように八重桜が満開になった頃、赤いベレー帽がよく似合うアオゲラのペアが「トゥルルルルルルル」とリズミカルにドラミングを響かせ八重桜の幹に巣作りの真っ最中である。
しばし穴掘りを注視する。♀が黙々と穴掘りをしているが、♂は現場監督のように時折、進み具合を確認に訪れるだけでほとんど協力しないのである。
自分のことを棚に上げ「この甲斐性なしめ!」と、♂をにらんでいたら、どうやらそうではないらしい。
事情通によると、穴掘りのきっかけは「私、ここが気に入ったわ」と、まず♀が掘り始め、暫くそれを眺めていた♂が意を体し「ここ良いんだね?」と、ラグビーボール大の大きさの穴を猛烈な勢いで掘り進めていき巣穴を完成させるのだという。
アオゲラ(緑啄木鳥、キツツキ目キツツキ科アオゲラ属)
留鳥、本州から屋久島まで生息する日本固有種である。
平地から山地の林で生息。
大きさは約29㎝。
頭部に赤いベレー帽のような帽子をかぶり、顎線も赤色。翼は黄緑色で覆われている。
一回で約5~6個の卵を産み雌雄が交代で抱卵する。
ちなみに、アオゲラの名の由来は、緑色を青ともいうのでアオゲラと呼ばれるようになったそうだ。
この時の撮影技法(情景描写)
アオゲラのアップだと、何処で撮っても似たような画になるので、今回は八重桜という絶好の場所での巣作りである。
狙いは満開の八重桜とアオゲラである。
撮影ポイントは4つ。
①満開の桜が効果的に写り込むアングル。
②巣の入り口がよく見えるアングル。
③仲睦まじいペア。
④雲の動きを見極める。
あとは、この4つの条件を満たすベストポジションを探し出すだけである。
カメラ設定
露出設定マニュアル露出、シャッタースピード1/200秒,絞りF6.3、ISO800
使用機材
Canon 5D MarkⅡ、300ミリF4 IS
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
忘れ雪のスプリング・エフェメラル2010.05.21
4月16日、朝から冷たい雨が降り続いている。
夜7時過ぎ、麻布十番の取材先へ向かうカーラジオから耳を疑うようなアナウンスが聞こえてきた。
「都心ではこれから雪に変わるかもしれません・・・」。
もしも都心で雪が降ることがあれば41年振りの遅い雪であるという。
ゆっくり動く車のワイパーをぼんやりと眺めながら、「そういえば、昨日まで取材に行っていた沖縄もこの時期にしては少し肌寒かったよな・・・」と、独り言を呟きながら取材先へ向かう。
真夜中の3時過ぎ。
急ぎ仕事の画像処理を終えると、「・・・もしかして」と、カーテン越しに窓の外を見渡す。
雪!それも41年振りの遅い雪が降っている。
この季節はずれの「忘れ雪」にもはや心穏やかではいられないけれど、ここはひとまず眠らねばと急ぎベッドに潜り込む「この雪の中、諸喝采の花が咲き乱れたあの場所のツマキチョウたちは今頃どうしているのだろう・・・か・z・・zzz」。
朝6時、バネ仕掛けのように跳ね起きる。
ニコンD300にVR18~105 mmのズームレンズをもどかしげに装着する。
忘れ雪、寒さに耐えるツマキチョウの一瞬の輝きを見逃してなるものかとドタバタと長靴に足を突っ込み転がるように「忘れ雪のスプリング・エフェメラル」にあいに行く。
ツマキチョウ(チョウ目・シロキチョウ科)
♂は翅を開けると前翅表面の先端が橙色のとてもお洒落な配色をしています。
♀は前翅表面の先端はかすかな黒い模様と白地の少し渋めの色合いです。後翅裏は写真のように雌雄とも迷彩色の編目模様になっています。
年一回、春先に(3月から5月)見られることから春の妖精「スプリング・エフェメラル」(春の儚い命などの意)とも呼ばれています。
この時の撮影技法
雪の重みで倒れた諸喝采の花を注意深く見ていくと、ほどなく目的のツマキチョウを見つけることが出来ました。
今回のキーポイントは、雪景色なのに冬ではなく春「忘れ雪」の季節感をいかに表現できるか。
雪が雨に変わり、傘と長靴そしてビニールシートを準備した。
また、この環境下ではレンズ交換は極力避けたかったのでニコンD300にVR18~105 mmのズームレンズをチョイス。
雨でぬかるんだ地面にシートを敷き、左手に傘をさし腹這い状態で泥だらけになりながら撮影した図である。
傍目には滑稽このうえなしである。
このケース、アングルファインダーを使ってもよいのだが何故だか臨場感に欠けるように思え、近頃は滅多に使わなくなってしまった。
理由は今起きていることに対し同じ目線で対峙したいからである。
このように苦労して撮影した写真には思い入れが強く、独りよがりの画になりがちであるが、公開の気分は清水の舞台からエイッである。(笑い)
果たして、脇役の水滴や桜の花びらがいいアクセントになり、主役のツマキチョウを盛り上げてくれただろうか?
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/50秒,絞りF6.3(-0.3)ISO400
使用機材
Nikon D300、VR18~105 mmズームレンズ(98mmで使用)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
麗しい風景(オオワシの棲む森)2010.04.28
胸の底にどっぷりと浸かっていたオオワシへの想いが叶い、晴れ晴れとした気持ちで流氷の海から下船した。
その日の午後、オオワシの棲む森に立つ。
目の前の樹上には数羽のオオワシが静かに休息している。
澄み渡る青空の下、辺りはシーンと静まりかえり時折「ドサッ」と雪の落ちる音が聞こえるのみだ。
ただただボーッと麗しい風景に見とれていると、オオワシの樹の下にエゾシカの親子がゆっくりと現れた。
オオワシ(大鷲)
タカ目タカ科オジロワシ属、絶滅危惧類Ⅱ種(環境省鳥類レッドリスト)
♂ 88cm ♀ 103cm(220-250cm)体色は黒と白で、嘴はオレンジがかった黄色。
翼を広げると優に2メートルを超え日本に棲む猛禽では最大の鳥。
日本へは越冬の為に飛来する冬鳥。
北海道ではごく少数が繁殖するそうだ。
写真のように越冬地では水辺の森の樹上で休む。
主食は主に魚類のフィツシュバードであるが、まれに死んだ野ウサギやエゾジカなどの肉も食べる。
この時の撮影技法
不思議と天気には恵まれるらしく、此処でも青空の下での撮影となった。
オオワシはいったいどんな場所で休息しているのであろうか?
「見てみたいな」と思い行動しました。
そして、探し当てたその空間は私にとってまさに「麗しい風景」そのものでした。
まずは主役のオオワシのアップから撮影開始、そして周りの環境をカメラに納め終わると、突然エゾシカの親子がゆっくりと現れました。
主役はオオワシなれどエゾシカの出現に私のテーマである「麗しい風景」に変更です。
素早く70~200ズームレンズでフレーミングをしてエゾシカの動きだけを注視する。
理想的な場所に移動し、母シカ?が顔を上げた瞬間にシャッターを押した。
この突然のエゾシカ出現により、オオワシの棲む森の存在感をより一層引き立ててくれたように感じますがいかがでしょうか。
カメラ設定
露出設定マニュアル露出、シャッタースピード1/500秒,絞りF9.5、ISO125
使用機材
Canon 1Ds MarkⅡ、70~200ミリF2.8ISレンズ(焦点距離130mm)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
カミソリの海へ2010.03.26
見てみたい・・・と思った。
その鳥はアムール川を離れた流氷と共にオホーツク海にやって来るという。
何時の日だったか記憶は曖昧ではあるが、日本で一番小さな野鳥「キクイタダキ」を目にしたその日から始まった。
ならば日本で一番大きいな野鳥のひとつを見てみたいと思うのが人の常だ、と・・・。
都合良く自分に言い聞かせた故、とうとう羅臼へ来てしまった意である。
まだ夜の明けきらぬ港に立つ、潮風はやはりキリリと冷たくて、髭剃り後のチクリとした痛みが頬に当たる感あり。
デジカメを抱いていざカミソリの海へ。
この時の撮影技法
出航後のスナップの一コマです。
5時30分出航、日の出は6時8分。
薄ボンヤリと国後島が浮かび上がってきた5時50分頃、この画のシャッターを押した。
その時のインスピレーションは、待ち焦がれたワクワク感「逸る気持ち」そんな漠然とした思いを画に出来たら・・・と、考えました。
そこで今回の撮影ポイントは2つ。
①「逸る気持ちのワクワク感」の表現。
②「夜明け前の厳冬海」の表現。
①の表現方法はブルー(寒色系)との補色関係にある船のライトの暖かい色味(暖色系)でワクワク感を演出。
全体の寒々とした色調の中で、ワンポイントの暖かい光が画を引き締めてくれるように感じました。
②の表現方法。
夜明け前の仄暗い雰囲気をローキートーン(-露光による暗い画面の調子)で調整する。
そこで露出はマニュアルで-補正を行い、ホワイトバランスは現像時に蒼海色に調整する。
さらに人の立ち位置バランスも重要と思い、望みの位置に人影が移動するのを待ってスローシャッター1/13を押した。
さて「逸る気持ち」が画に出来ただろうか?
旅のスナップとフィールドノート
私は、道中の雑感スナップを数多く撮ります。
たとえば今回の場合、港へ向かう前に宿の周りでキタキツネをパチリ、港に着いて船をパチリ、出航の様子をパチリ、餌付けの魚の種類をパチリ、漁船内の様子、漁船から見た景色。
宿に帰ると、その土地で食べたもの、その土地で気になった雑誌、パンフレットなどなど手当たり次第にパチリパチリとスナップする。
当然デジタルカメラの画像データには時刻がしっかりと時系列で記録され、後々の手引きメモとして残されているからです。
それと平行して、フィールドノートに時間の許す限り撮影内容を、メモします。
内容は「何時、何処で、誰が、何を、どうした」などを簡潔にメモします。
勿論、地元の人に聞いた話の内容などもメモします。数日後、数年後、膨大な画像データの中から必要な画像データを、フィールドノートのメモを頼りに素早く探し出せるという仕掛けなのです。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/13秒,絞りF4(-補正)ISO400
使用機材
Canon EOS 5D、24~70ミリF4IS,レンズ(24mmで使用)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家