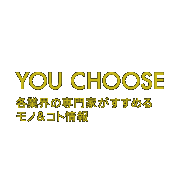- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
捕食者の輝きを放つ「オオスズメバチ」2009.10.16
クヌギの樹の下で、S氏が何かを叫んで手招きしているので駆けつけると、
ハラビロカマキリが横たわっていた。
聞くと「オオスズメバチの落とし物」とのこと。
おそらくクヌギの高所で狩ったものの重すぎて落としてしまったらしい。
二人して覗き込んでいると、やがて落とし主が羽音を響かせて背後から現れた。
我々は少しだけ後ずさりして様子を窺っていると、
オオスズメバチはふわりとハラビロカマキリの近くに舞い降りた。
恐る恐る5㎝程の近距離にカメラを置きレリーズでシャッターチャンスを待った。
一回では運べないとみて頭部、胸部、お腹、
と手際よく数回に分けて肉団子にして運び去った。
息の詰まるような緊張感のあいだ、
オオスズメバチは捕食者の輝きを放っていた。
オオスズメバチ
世界最大種で、体長:女王バチ40~45mm,働きバチ27~40mm,オスバチ35~40mm、
攻撃力、毒性もきわめて強い。
秋口(9月~10月)になる大きくなったコロニーの幼虫や蛹の餌集めで忙しくなり、
集団でミツバチやキイロスズメバチなどの巣を襲います。
よってこの時期キイロスズメバチなどは天敵のオオスズメバチの襲撃にそなえ
絶えず見張り番をおき巣に近づく者に対し攻撃をしかけます。
このような理由から秋口には被害者が多発することになります。
都市部でキイロスズメバチが増えた原因として
天敵のオオスズメバチが少なくなり
生態系のバランスが壊れてしまったのが原因ではないかと言われています。
オオスズメバチは見るからに怖い顔をしていますが決して無益な攻撃はしません。
人があやまって巣に近づくと体の周りを飛び回り、
さらに巣に近づくと大顎をカチカチ鳴らし近づくなと警告を発します。
その時はゆっくりと後ずさりをしてその場を離れることです。
間違っても手で追い払ったりしないことです。
この時の撮影技法
オオスズメバチとの息詰まるような緊張感がたまらなく好きで、
季節ごとに思い描くシーンをシュミレーションしていますが、
何故か不思議と思い描いたシーンに遭遇します。
今までオオスズメバチの「食うか食われるか」のシーンを幾度となくカメラに納めてきましたが、
幸運にもこの週は3日連続で「オオスズメバチ同士の死闘」、
「セミと共に謎の絶命」、そして「カマキリの解体シーン」に巡り会えました。
思うに「こんなシーンが撮りたい」と念じることにより、
予め被写体の予備知識やカメラ機材の準備しておくことこそがシャッターチャンスを撮り逃さない、
撮影技法の重要なファクターかもしれませんね。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/500秒,絞りF4.5、ISO800。
使用機材
Canon40D、シグマ8mmフィッシュアイレンズ+1.5Xテレコン。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
キチョウと萩2009.10.15
秋の七草のひとつ「萩」の字は
クサカンムリに秋と書く日本生まれの和製漢字ですが、
『万葉集』の中で萩の花の歌を詠んだものが一番多く141首ほどあるといわれています。
花の人気も高く此処の神社境内にも縁起ものとしてなのだろうか2対植えられています。
萩はキチョウの食草(マメ科)であることから、
数頭のキチョウが吸蜜、交尾、産卵にここの萩に依存しています。
写真は蛹から羽化したばかりのキチョウの交尾です。
キチョウの♂は今か今かと蛹の羽化を待ち構えるるように、
常時数頭が代わる代わる確認に訪れます。
その羽化直後の交尾シーンにはなかなか巡り会えず悔しい思いを募らせていましたが、
今回やっとその決定的瞬間が訪れました。
撮影技法
キチョウの羽化直後の交尾シーンはお互いが翅を閉じているため肝心の部分が確認出来ません。
観察の結果、ライバルの♂がちょっかいを仕掛けた瞬間だけ翅をバタバタと開くので
そこを狙うことにしました。
8ミリ魚眼レンズ+1.4xテレコンをキチョウの下の方にセット。
ストロボはサンパックPF20XD2灯使用、一灯は斜め右から三脚にセットして、
もう一灯は手持ちで影の出方を調整しらがら内蔵ストロボに同調させて、その瞬間を待ち構えた。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/120秒,絞りF18、ISO400。
使用機材
Canon40D、シグマ8mmフィッシュアイレンズ+1.5Xテレコン、内蔵ストロボ+外部サンパックPF20XDストロボ2灯、三脚。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
曼珠沙華に遊ぶオナガサナエ2009.10.14
彼岸花、別名「曼珠沙華」の名所「巾着田」に向かった。場所は西武池袋線高麗(こま)駅下車、徒歩約15分程行ったところある。
約100万本以上の真赤な花が一斉に秋風に揺れる様はまさに圧巻だ。
そこで今回は曼珠沙華に遊ぶ生き物にターゲットを絞り探してみることにした。
3時間程経った頃だろうか、魅惑的な色に誘われるように中型のトンボが留まった。
美しい緑色の複眼と尾部付属器の長さからみて「オナガサナエ」である!すかさず一枚目を撮影、さらにそーっと忍び寄り2枚目を、息を殺してさらににじり寄る。
頭の中は嬉しさと表現方法でオーバーヒート寸前だ。
オナガサナエ(尾長早苗)サナエ科
日本特産種で、体長は60ミリ前後の中型のトンボ。河原の石の上や枝先などにじっと静止していることがおおく警戒心が薄い。
察するに、この撮影場所が「高麗川」沿いのため、曼珠沙華に留まったのではないかと推測される。
成熟個体の放つ鮮やかな緑色の複眼と、長い尾がとても美しいトンボで曼珠沙華の赤い色とのハーモニーがとても素敵だ。
この時の撮影技法
警戒心の薄いオナガサナエはまるでプロのモデルみたいで撮りやすい。望遠レンズ、マクロレンズ、広角レンズと色々と試すことが可能だ。
今回は曼珠沙華の鮮やかな赤が主役で、オナガサナエは脇役である。しかしオナガサナエには主役を食うほどの存在感が感じられ小さく画面左上部に配置した。そして、オナガサナエの背景に少しだけ高麗川の水の青を隠し味程度に取り入れ、85ミリレンズ望遠レンズの圧縮効果で曼珠沙華のボリューム感を演出した。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/125秒,絞りF5、ISO100。
使用機材
使用機材:Canon 1Ds MarkⅡ、24~105ミリISレンズ(84ミリで使用)。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
鬼のパンツをはいたオニヤンマ2009.09.28
「水と米」の取材で南魚沼の「龍言」に投宿している。
昨夜はしこたま旨い酒「八海山」を呷ったはずだが、
この日も目覚め良く浴衣姿のまま、
いそいそと2台のカメラをぶら下げて仄暗い部屋を抜けだした。
朝焼けの中庭に出ると、
まだ人影はなく予定の撮影も順調に進んでいたが・・・、
何かしら足下で蠢いている。
目を懲らすと蠢く正体は日本最大のトンボ「オニヤンマ」。
約4~5頭程が産卵の真最中である。
幸い当初の目的であったカットは撮り終えていたので急遽、
鬼のパンツをはいたオニヤンマに変更。
オニヤンマ(鬼蜻蜓、馬大頭)
日本最大種、トンボ目オニヤンマ科、
頭部から腹の先端まで♀は♂より大きく95~110mmほど。
名前の由来は、
黒と黄の段だら模様から虎の皮の褌を締めた鬼を連想させる事から、
オニヤンマという名前がついたとのこと。
ちなみに日本最小トンボは一円玉(20mm)に収まるハッチョウトンボ(18mm)です。
★8月吉日、成美堂出版から『一冊でわかる楽器ガイド』が出版されました。
この本は「楽器へのいざない」をメインテーマに
オーケストラに使われる楽器の音の出る仕組み、歴史、音域にまつわるエピソードなどが満載です。
私は表紙や楽器などの写真を担当。
音楽に興味のあるか方は書店にてご覧頂けると幸いです。
この時の撮影技法
産卵時の臨場感の表現がポイントです。
暗がりの中での産卵シーンはストロボが必須。
幸いニコンデジタルカメラD300は内蔵ストロボがマニユアル設定可能なので、
緊急手段として内蔵ストロボをマニュアルに設定(ストロボオートでは光のコントロールが難しい)。
もともとトンボは動く物には敏感に反応しますが、
そ~っと距離を詰めればかなり近くまで寄れます。
せせらぎの中に入り大股開きで撮影していたら、
なんと浴衣の中まで入って来ました。
あっけにとられつつもノーファインダーでカメラボディーが水に触れるほど水面ギリギリまで低くセット。
オニヤンマの産卵管が川底に触れた瞬間に産卵が行われるので、
その瞬間がしっかりと裸眼で確認できる約50㎝まで近づき、
リズミカルな産卵のタイミング合わせて撮影しました。
手の届く位置まで近づいてオニヤンマと同じ目線ならば、
離れて撮る場合よりも臨場感がより表現出来るように感じますが如何でしょうか?
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/45秒,絞りF8、ISO400、内蔵ストロボ使用マニュアル設定
使用機材
Nikon D300、18~55mmズームレンズ。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
息絶えるバルタン星人2009.09.14
ムモンホソアシナガバチのコロニーを目指して急ぎ足で歩いていると、
ポトリと目の前に何か落ちてきました。
近づいて覗き込むと
アブラゼミが樹の表皮の一片を抱えて今にも息絶えようとしています。
「!?・・・、夏もそろそろ終わりかな・・・」などと思いつつも、
ふと何気ない日常の一コマに
夏の終わりの哀愁を感じカメラを構える事にしました。
アブラゼミは世界でも珍しい翅全体が不透明のセミで、
日本の夏を象徴するセミの一種です。
成虫の寿命は約1~2週間、
名前の由来は油で揚げ物をするときの音が
アブラゼミの鳴き声に似ている事からアブラゼミと呼ばれています。
天敵は鳥、ハチなどの昆虫、前回の冬虫夏草などの菌類、
さらには天敵と言えるか解りませんが、
写真に小さく赤く写り込んでいるタカラダニ
(セミに赤いダニがくっついていると宝物を抱えているように見えるということから、
タカラダニと言う説がある)
など。
それにしても、このバルタン星人、無事に命のバトンは出来たのだろうか?
と、・・・夏の終わりに独り想う。
笑えない話
種類は違うがクマゼミの産卵で笑えないニュースがありました。
西日本ではクマゼミが大量発生して
「光ファイバーケーブルを枯れ枝と間違えて産卵したために断線被害が多発」
の報道。
インターネットにも思わぬ天敵がいたものです。
この時の撮影技法
息絶えるバルタン星人の存在感を如何に表現出来るかがポイント。
イメージ表現の一例としてデフォルメされたセミと、
かつ多少なりとも背景も解るような深い被写界深度が欲しくて、
ドアスコープの様な形をした虫の目レンズの「魚露目」を使用。
セミの前約2㎝にカメラを地面にセット。
接写リングやテレコンをかませるとレンズはかなり暗くなるので、
セルフタイマーを2秒にセットしてカメラブレを軽減。最後に静かにシャッターを押した。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/4秒,絞りF18、ISO 200
使用機材
Nikon D300、接写リング12ミリ+1.5Xテレコン+ニッコール28~85ミリズームレンズ(45ミリで使用)+魚露目レンズ。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家