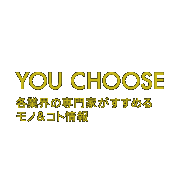- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
赤いホッペ(ソメイヨシノの蕾)2011.03.28
三寒四温に揺さぶられ、一片の花びらが目覚めたようだ。
ソメイヨシノの蕾の大きさは約1センチ、ちょっぴり覗いた花びらは北国の子供のホッペのように赤い。
サクラは散り際が美しいともいわれるが・・・。
春の目覚めのホッペもまたすてがたい趣がある。
さて、ここから季節は一気に蕾を開かせ、赤いホッペから薄紅色、そして白色に近づき桜吹雪へと駆け抜けて行く。
以前、公開した福島の「三春の滝桜」目立った被害もなく、元気とのこと。
こんな時だからこそ今年も出かけてみようかとも思っている。
ソメイヨシノ「染井吉野」
エゾヒガン系とオオヤマザクラとの交配で生まれたサクラの園芸品種。
「吉野桜」と表記することもある。
花弁は5枚。
エゾヒガン系と同様に、葉より早く花が咲く性質と、オオシマザクラの大きな花びらを併せ持った品種で、満開時には大きな花で樹全体を彩る。
名の由来は、江戸末期から明治初期、江戸の染井村「現在の東京都豊島区駒込」の植木屋が品種改良した園芸品種。
当初、奈良県の桜の名所「吉野山」にちなんで「吉野桜(ヤマザクラの意)」として売り出していたが、「吉野桜」では誤解を招くとして、明治33年、東京帝室博物館天産部の職員であった藤野寄命博士が上野公園のサクラを調査し「染井吉野(ソメイヨシノ)」として『日本園芸雑誌』において命名。
ちなみに、全国のソメイヨシノは一本のマザー木から接ぎ木されたクローンであり同じ遺伝子をもつ。
この時の撮影技法(手持ち撮影にてマクロ接写するコツ)
被写体がここまで小さいと、手持ち撮影時には「カメラブレ」や「被写体ブレ」でフォーカスがとても難しくなります。
そこで、チョットしたコツをご覧の写真で説明します。
方法は実にカンタン。
まず、蕾の下5センチ程を左指でつまみ、レンズの先端部分と一緒にホールドします。
すると、揺れていた蕾がレンズの揺れと同調し、ピタリと揺れが収まるという塩梅です。
あとは、ゆっくりとカメラ本体を前後してフォーカスします。
その時、シャッターは霜が降りるように優しく押します。
決して勢い余って強くシャッターを押すのはブレの量産に繋がりますから御法度です。
さて、今回の道具立ては、1センチ程の蕾から覗く花びらを撮影するために、キヤノンの倍率5倍まで撮影できる「65ミリマクロレンズ」をチョイスしました。
このレンズは少し特殊です。
なんとフォーカスは、カメラを前後して行います。最初はまごつきますが、慣れてしまえば小さな被写体には重宝この上なしです。
撮影地:いこいの森公園、西東京市(田無市)「以前は原子核研究所址。東京大学原子核研究所、通称核研(INS)、1955年7月から1997年3月までの43年間にわたり原子核、素粒子、宇宙線の研究所として創設された。
ここで育った研究者は現在、世界各地で活躍している」と刻まれている(要約)。
カメラ設定
絞り値:F/11、シャッタースピード:1/200秒,露出モード:マニュアル、露出補正:−1/2段、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ISO感度設定:200、ピクチャースタイル:ポートレート、焦点距離65mm, マクロリングライトMR-14EXストロボ調光補正:-1, スピードライト580EX調光補正:0
使用機材
Canon 5D MarkⅡ、CANON MP65mmF2.8 !-5x マクロフォト、マクロリングライトMR-14EX(黒色のテープで発行部を覆い縮小して使用), スピードライト580EX, エツミストロボディフューザーG6、三脚ベンロカーボンネオフレックスC-298m8(580EXのスタンドとして使用)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
木枯らし2010.12.28
年の瀬。誰もいなくなった公園で、めっきり少なくなった虫を未練がましく探していたけれど「♪夕焼け小焼け」が流れてきたので、カラスと一緒に帰り支度を始めた。
すると、突然風が吹き出し、落ち葉がザワザワと舞い上がりはじめた。
それからはもう、まるで堰を切ったようにみるみる葉っぱ増水し、荒れ狂う川の濁流のように木々に激しくぶち当たり砕け散り舞い上がった。
こりゃ~凄い!と、バッグに仕舞いかけたカメラを取り出し撮影ポイントを探るが、ふと、舞い踊る落ち葉を見て、♪をつけるとしたら何が良かろうか?と、よけいな事を考え始めたのである・・・。
「う~む、♪コンチネンタルタンゴ?いやいやアフリカ系のビートが効いた♪アルゼンチンタンゴが良いかな?いやいや・・・♪だんご三兄弟、それとも♪木枯らし紋次郎。おいおい、音楽に疎いのがバレバレだねぇ」
などと、誰もいなくなった薄暗い公園でひとりブツブツニヤニヤ。
・・・・・
「カシャ!カシャ!」
木枯らしとは
太平洋側地域に晩秋から初冬にかけて、冷たい北からの強風(風速8m/s以上)が吹く季節風のことをいう。
強い風で木の葉を落とし枯れ木にするので「木枯らし」の説や「木嵐」が転じたとの説もあるようだ。
初冬に吹き荒れた木枯らしの気圧配置は長続きせず、翌日には穏やかな小春日和になりやすいともいわれる。
この時の撮影技法(ブレについて)
ブレの原理が理解できると、「瞬間をキッチリ止めたい」「動きのある写真を撮りたい」などの、思い描く完成画を容易に具現化できるようになります。
ご存知のように、ブレには大きく分けて「被写体ブレ」と「カメラブレ(手ブレ)」があります。ブレを押さえ込むには「高速シャッター」「三脚」「カメラブレ補正レンズまたはカメラ内補正機構」「パン=流し撮り」などがあります。
1)ブレはレンズの焦点距離で異なる。
広角レンズと望遠レンズではカメラブレは異なります。例えば広角レンズ20mmでは1/20s以上、望遠レンズ300mmでは1/300s以上がカメラブレを防ぐ限界シャッタースピードと一般的には言われています。
すなわち、焦点距離と同じ値がシャッタースピードの下限値という訳です。
(勿論、経験を積むことによりその数値以下でも止められるようになります)
2)ブレ表現にはシャッタースピードの加減が重要
例えば、プロ野球の投手が投げたボールを、バッターが打ち返した瞬間を捕らえるには最低1/250s以上でなければバットに当たった様にみえる瞬間は撮れません。
完全に止めるには約1/1500s以上が必要です(条件によって異なる)。
もし、1/60sならばボールとバットは消えてしまうことになります。
また、人通りの激しい繁華街で三脚を使いシャッタースピード30秒以上で撮影を行うと、30秒間じっとして動かない物以外は総て消えてしまい、無人の不思議な街として撮影出来てしまうのです。
この様に、シャッタースピードの加減ひとつで表現方法が飛躍的に広がります。
3)動きを表現する二つの方法(フォロー・パンとフィックス)
A、フォロー・パン(Pan=流し撮りのこと:被写体の動きに合わせ同一方向へカメラを振る)
例えば、1/30sでカメラを疾走する車と同じ方向へパンして撮影を行うと、車の車輪は回りかつ背景は流れている。
しかし車体はブレてないような写真が撮れます。
B、フィックス(カメラ固定)
カメラを三脚などで固定して撮影。
ご存知のとおり、静止したもの以外は被写体の動きの速さでブレ幅が異なります。
例えば、風景写真の場合。木々の葉っぱが風で揺れていると
低速シャッター(ブレは風の強さで異なる)では葉っぱが揺れて写り、その場の情景をドラマチックに仕上げるスパイスの役割を持たせることもあります。
今回の写真は、あえて被写体ブレとカメラブレの両方とを持ち合わせたカットをセレクトしました。
本来ならば破棄してしまうカットですが現場の雰囲気を一番表していたので、あえてこのカットをセレクトしたというわけです。
カメラ設定
絞り値:F/16、シャッタースピード:1/30秒,露出モード:マニュアル、露出補正:-2段、ホワイトバランス:晴天、測光モード:マルチパターン測光、ISO感度設定:ISO 400、焦点距離100mm
使用機材
Nikon D300、AF-S NIKKOR VR 70-300mm F/4.5-5.6G
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
狩りから戻ったクロスズメバチ2010.12.14
恐る恐る、どれだけの震動で飛び出すのだろうか?
と、巣穴から2メートル程で「ドン!ドン!」と踏み鳴らすも反応がない。
ならば30㎝程では如何に、と「ドン!ドン!」、案の定スクランブルがかかり後ずさり。
でも、威嚇性も攻撃性も弱いので巣穴から3メートル程に避難しつつ、何に対して反撃をしかけるかと観察する。
やはり、黒色のカメラボディー、ストロボの黒色の箇所、レンズ(ハチ自身が映り込むからか?)などに集中する。
暫くするとハチの興奮も落ち着き、巣穴から50cmほどの至近距離から観察を続行。
ときおり巣穴から顔を出し外の様子をうかがう者、重そうに肉団子やアオマツムシの足らしき物を持ち帰る者、巣の中から土や枯れ葉を運び出す者、レイジー(怠慢)らしき者、飛び出しと同時に空中衝突する者などなど、実に興味深く喜悦満面でシャッターを押す。
クロスズメバチ(黒雀蜂)ハチ目、クロスズメバチ属。
体長は女王バチ15mm~16mm,働きバチ10~12mm,オス12~14mm。
スズメバチの中では小型。
全身は黒く、白色または淡黄色の横縞模様。
北海道、本州、四国、 九州、奄美大島など広く分布する。
おもに地中に大きな巣をつくる。
地方により呼び方が、スガレ、ヘボ、タカブなどと呼ばれ一部では食用とされる。
3月下旬頃から女王バチは活動を開始し、働き蜂は6月頃羽化、新女王蜂や雄蜂は10月~12月に羽化する。
ハエ、アブ、ガの幼虫、蜘蛛などの小さな昆虫を主に狩り、幼虫の餌として与える。
成虫の餌は、樹液や終齢幼虫の唾液腺から分泌された栄養液。
毒性、威嚇性、攻撃性は弱い。
この時の撮影技法(道具立て)
獲物を持ち帰るクロスズメバチを、被写界深度の深いフィッシュアイレンズで狙うことにした。
おとなしいといっても相手はスズメバチ。
そこで、撮影シミュレーションを行い必要な道具立てを考えます。
それはまるで「あれもこれも」とお菓子をリュックに詰め込む、高揚した小学生の頃の遠足前夜です。
撮影当日、パンパンに膨らんだカメラバックを背負い、脇目もふらず一心に自転車を転がす僕がおります。
①カメラを地面にセット
カメラを地面に置く時に便利なカメラ座布団(お手製)を使用。これは好きな角度に簡単に素早く設定出来る優れもの。カメラは縦位置で巣穴7㎝程にセット。
②魚眼レンズに外部ストロボ2灯
魚眼レンズは画角が広いので、ストロボをレンズの前方には出せない。
ギリギリの位置決めのため、ローアングルの自由度が効く三脚ベンロカーボンネオフレックスC-298m8にCANON SPEEDLITE 580EX+エツミストロボディフューザーG6をセット(魚眼レンズ用に拡散ディフューザーとして)カメラ上部にセット。
もう一灯の580EXは左側にセット。
CANON SPEEDLITE TRANSMITTER ST-E2でスレーブ。
さらに、小型のSUNPAK PF20XD+ミニ三脚SLIK PRO-MINI Ⅲをレンズ横からマニュアル光量で使用。
③シャッターは遠隔操作
「ドン!ドン!」で怒り狂ったクロスズメバチを、離れた位置から遠隔操作ができるCANON WIRELESS CONTROLLER LS5を使用。
ハチが落ち着くと、レンズ横から覗き獲物を抱えたクロスズメバチが巣に飛び込むタイミングをはかる。
カメラ設定
絞り値:F/14、シャッタースピード:1/250秒,露出モード:マニュアル、露出補正:-1/3段、測光モード:スポット測光、ISO感度設定:ISO 400、
使用機材
CANON 40D、SIGMA 8mm f/8 1:3.5 EX DG FISHEYE、KENKO 1.5XTEREPURUS MC、CANON WIRELESS CONTROLLER LS5 、CANON SPEEDLITE TRANSMITTER ST-E2、CANON SPEEDLITE 580EX2灯使用+エツミストロボディフューザーG6、三脚ベンロカーボンネオフレックスC-298m8、ミニストロボSUNPAK PF20XD+ミニ三脚SLIK PRO-MINI Ⅲ、お手製カメラ座布団。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
秋を告げるクロナガアリ2010.11.30
「ソイヤソイヤ」と秋の収穫祭が行われていた。
と、いっても御輿(エノコログサのタネ)の上で見事な足技を披露しているのは、日本人と同じイネ科植物を食す唯一のクロナガアリ。
今年の猛暑も涼しい地中で過ごしていたが、秋の収穫期に合わせ地上に現れたのだ。
私は、祭囃子に促されるように最前列のカメラマン席にローアングルで陣取った。
クロナガアリ(黒長蟻)ハチ目・アリ科・フタフシアリ亜科。
働きアリの体長は約4~5mm、女王アリ約10㎜。
地中深くに巣を作る。体は黒色で、頭部と胸部は艶がなく、丸い腹部のみ艶がある。
日本のアリは約270種いるといわれるが、このクロナガアリのみが唯一、イネ科植物のオヒシバやエノコログサなどの種子を食料とする。
本州、四国、九州、屋久島などで年2回ほど見ることができる。
一回目は羽アリになり4~5月の良く晴れた日に一日だけの婚約飛行を行う。
二回目はイネ科植物の種子が落ちる秋に再び地上に現れ、食料となる種子を拾い集め巣に運び込む。
運び込まれた種子は精米担当アリに渡され、カビたり腐ったりしないように皮を剥き、ピカピカに磨いて食料として貯蔵する。
収穫が終わると再び本来の地中生活にもどる。
この時の撮影技法(被写界深度とは)
被写界深度とは一言で言えば「ピントの合う範囲」のことを指します。
写真撮影技術を理解するうえで「被写界深度」はとても重要なアイテムのひとつです。
絞り、焦点距離、被写体との距離、撮像センサーサイズと密接な関係にあります。
●絞り
仮に、今回使った標準マクロレンズの絞りがF2.8~F22までだとします。
開放絞りとはF2.8のことを指します。
この絞りで撮影するとピントを合わせた前後の範囲はボケるので「被写界深度が浅い」といいます。
逆にF22だと、絞り込むといいます。
ピントを合わせた被写体の前後が、かなりの範囲までピントが合ったように見えるのでの「被写界深度が深い」といいます。
●焦点距離
広角レンズと望遠レンズとでは被写界深度が異なります。
広角レンズは被写界深度が深いレンズともいえます。
開放でもそこそこ被写界深度は深く、さらに絞り込む事により被写体の手前から背景まで明確にピントが合ったように見えるので「被写界深度が深いレンズ」または「パンフォーカス」といいます。
逆に、望遠レンズは絞り込んでもピントの合った前後の範囲は狭いので「被写界深度が浅いレンズ」ともいえます。
●被写体との距離
至近距離、すなわちマクロレズなどで接写を行うと、ピントの合う前後の範囲が極端に狭くなります。
上の写真ではF16まで絞り込み被写界深度を深くしていますが、ここまで絞り込んでも「接写では被写界深度が浅くなる」といえます。
●撮像センサーサイズ
撮像センサーサイズの違いでも被写界深度は異なります。
撮像センサーの小さな「コンパクトデジタルカメラは被写界深度が深い」といえます。
逆に「35㎜フルサイズデジタルカメラは被写界深度が浅い」といえます。
以上、少し説明が長くなりましたが、初心者脱出の切り札は「被写界深度を理解」する事だといっても過言ではありません。
今までの、カメラまかせの撮影から脱却して、自分の意志でカメラを操るマニュアル設定。そこにこそ自分の思い描いた画作りのヒントが隠されています。
今回の写真では、動き回る3匹のアリにある程度のピントがくるようにF16まで絞り込みましたが、それでも接写ではピントの合った前後の範囲は狭く、出来れば最大値のF22まで絞り込みたいところです。
でも、すでにF16まで絞ってしまったために回折現象が起き描写が若干甘くなっています。
しかし、それを覚悟してまでも被写界深度を稼ぐためにF16まで絞り込みました。
何度も言うようですが、接写時の被写界深度はとても浅くデリケートなピント合わせが必要なのです。
(回折現象についてはいずれ・・・)
カメラ設定
露出モード:マニュアル、絞り値:F/16、シャッタースピード:1/250秒、露出補正:±0、測光モード:スポット測光、ISO感度設定:ISO 640、内蔵ストロボ:±0、コマンダー設定外部ストロボ+1/3補正
使用機材
Nikon D300、AF Micro NIKKOR 60mm 1:2.8、Nikon SPEEDLIGHT SB-600、内蔵ストロボ:エツミポップアップストロボディフューザー(ナチュラル) E-6218、レジャーシート
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
思案顔のオンブバッタ2010.10.13
秋口、ごく普通に見られる雌のオンブバッタに出会った。
なんだか、他の個体よりも警戒心が少ないようだ。
彼女との距離は2メートル程。
早速、私は総ての動作をスローモーションに切り替え、抜き足差し足で慎重に間合いを詰めた。
そろ~り、と後ろ姿、横顔、そして「面構えは如何に」と正面に回り込み対峙する。
すると、彼女はおもむろに頬杖をつき、「ふ~っ」と深いため息をひとつと吐いた。
オンブバッタ(負飛蝗)バッタ目、オンブバッタ科、オンブバッタ亜科
日本全国に生息。
日当たりの良い平地の草原や半日陰の林縁などでごく普通に見られるバッタの仲間。
成虫は8月から12月頃に見られ、大きさは♂25㎜前後、♀42㎜前後。食草はキク科、シソ科、ダテ科、クズ、など。
ちなみに名前の由来は、和名の通りで小さな♂をオンブしている姿からオンブバッタ。
この時の撮影技法(虫に近づくコツABC)
写真を撮られる事が嫌いな方がいらっしゃるように、昆虫にも写真嫌いがいるようだ。
運悪く警戒心の強い個体を選んでしまったら、近寄ることすら難しく、カメラを向けただけで逃げられてしまいます。
そこで、今回は虫に近づくコツABCです。
1,モデルを選ぶ
同種の虫がたくさんいたら、出来るだけ警戒心の強くない個体を探す。
2,虫に近づく時にはスローモーション。
急な動きは虫を驚かせるので、極力動作はスローモーション。
3,カメラストラップに気を付けよう。
お目当ての虫を見つけて喜び勇んで接近。
でも、だらりと垂れ下がったカメラストラップが、枝葉などに当たって逃げられた、とならないために、だらりと垂れ下がった余分なカメラストラップは手に巻き付けるなどして予防しよう。
上記以外に、服の色(紫外線)、香水(フェロモン)、虫除けスプレーなど、昆虫の種、個体の性格もまちまちで一概にこれが良いとは言えませんが、大抵の場合は上記の3点を注意することにより、かなりの確率で接近可能です。
あとはじっくりと生態を観察して、狙ったシーンを待ち構えましょう。
(※注意:秋口にはスズメバチのコロニーが最大になり神経質です。黒い色の服や香水などは避けた方が懸命です)
カメラ設定
絞り値:F/9、シャッタースピード:1/200秒,露出モード:マニュアル、露出補正:-1/3段、測光モード:スポット測光、ISO感度設定:ISO 800、
使用機材
Nikon D300、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家