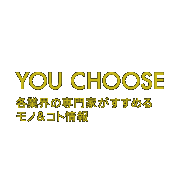- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
ハラビロカマキリとドジョウ2012.10.30
田んぼの脇を流れる小さな小川で、平泳ぎのアマガエルを撮影していたら、横からハラビロカマキリがフラフラと犬かきで入水してきた。まるで酔っぱらいのおじさんみたいに、視線が定まっていないように見えなんだか気持ち悪い。と、そこへ泥の中から♪ドジョウが出て来てこんにちは♪なんて、言ったか言わなかったか、泥の中から現れるなり、いきなりカマキリのお尻あたりをさかんにつつくではないか。(写真のシーン)それは、もしかしてハリガネムシがハラビロカマキリのお尻から出て来ているところであろうか?
ハラビロカマキリは自分の意志で入水したのではなく、寄生虫のハリガネムシに操られて水辺にやって来たと思われる。これはラッキー、とカメラを構えていたがドジョウにつつかれてもカマキリは気持ち良さそうに身を任せているだけで反応があまりない。それから1分位経っただろうか、私の期待は木っ端みじんに裏切られドジョウ君は何事も無かったように何処へとス〜ッと消えてしまった。お〜い!野田君チョットでもいから解散時期を、じゃなくて・・・ハリガネムシ君のお顔が出てきていたかどうか教えて頂戴、と聞けるものなら聞きたいのだがドジョウだけにドジョウにもならない。
ハリガネムシ
勇気のあるお方はコチラをどうぞ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ハリガネムシ
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=ハラビロカマキリ%E3%80%80ハリガネムシ&aq=-1&oq=&ei=UTF-8
この時の撮影技法(動きを表現する)
水に浮いているカマキリが動いているように見せるにはどうするか?
それは、カマキリが泳ぐ動作で水が波打ち光の波紋が出来る、そこでパチリ。
露出プログラムは、レンズが300mmという事で高速シャッターが切れるように絞り優先で1/500秒に設定。これでカマキリとドジョウの動きを止め、光の波紋が出た瞬間にシャッターを押せば動きが表現出来るという塩梅です。それと、300mmの望遠レンズなら被写体との距離間がとれるのでカマキリにもドジョウにも警戒される事無く密かに撮影出来るのです。
この日のカメラシステム
300mm望遠レンズと60mmマクロレンズを付けたカメラ2台態勢でどんなシーンでも素早く対処出来るように、リュックには24〜85mmスームレンズを付けたボデーとストロボが3台入っています。いざという時に、レンズ交換などしている余裕はありませんから。
カメラ設定
絞り値:F/4、シャッタースピード:1/500秒,ISO感度設定:400、露出プログラム:絞り優先、露出補正:-1/2、ホワイトバランス:オート、測光方式:評価測光、ピクチャースタイル:スタンダード、レンズ焦点距離:300mm
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Canon EOS 5D Mark II、EF300mm f/4L IS USM
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ニホンミツバチの防御2012.10.23
オオスズメバチがニホンミツバチの巣の前でホバリングをして、巣に帰って来るニホンミツバチを狩っていた。
首尾よく空中で捕まえると肉団子にして巣に持ち帰る、それを何回も繰り返していた。
観察すると、オオスズメバチにも狩りの上手下手がいる。
その中の下手なオオスズメバチが、じれたのか警戒の羽音を繰り返すニホンミツバチの巣の入り口に、うかつにも着陸をしてしまったのだ。
その瞬間、果敢な一匹のニホンミツバチがオオスズメバチに飛びかかり、それを合図に20〜30匹程が一斉にオオスズメバチに覆いかぶさった。
ニホンミツバチの熱殺蜂球とは
セイヨウミツバチは対抗の術をもっていないけれど、ニホンミツバチは長い歴史の中でオオスズメバチの攻撃から巣を防御する術をあみだしたのです。
スズメバチが巣に近づくと一斉に飛びかかり蜂球をつくり、体を震わし温度が上げ熱殺するのです。
熱殺蜂球の中の温度は約46〜47℃。オオスズメバチの高温上限致死温度は約45℃でニホンミツバチは約49℃。
ニホンミツバチは約47℃まで温度を上げ、この約2℃の致死温度差でオオスズメバチだけを蒸し殺すのだ。
写真は、その熱殺蜂球のシーンです。
もし、オオスズメバチが餌場フェロモンを発してしまったら、集団でオオスズメバチが襲って来るのでニホンミツバチの巣は壊滅してしまいます。
しかるに、オオスズメバチが餌場フェロモンを出す前に退治しなければならない、まさに生死をかけた緊迫の場面なのです。
この時の撮影技法(安全な撮影のための準備)
このシーンを撮影する為に考えておかなければならない準備があります。
▲ うかつに近づくと毒液を吹きかけられたり、刺される危険があるので黒っぽい服をやめ、白い服を着る。
▲ ストロボの連写は控える。キャノンの580EXは連写によるオーバーヒートでキセノンフラッシュランプが壊れてしまう危険性があるので出来るだけ冷ましながら冷静にシャッターを切る。
▲ 熱殺蜂球が始まったら比較的安全なので至近距離から撮影可能(ニホンミツバチはとてもおとなしい蜂なので近づいても安心)
▲ たえず他のスズメバチの気配を察知する。
どんな撮影でも、エキサイティングの場面では無中のあまり大胆な行動になりがちで事故の危険性が増します(近づきすぎて刺される、崖から落ちる、後ろに下がり屋根から落ちる、カメラを落とすなどなど実際にあった話しです)。冷静な行動を心がけましょう。
こぼれ話
教員の職をすて、花のジプシーになった叔父がいた。鹿児島から北海道まで花を求めて旅をするのである。
私が小学生の頃、実家の畑にも沢山の巣箱が置いてあってレンゲの花が咲き乱れる頃、最初の集蜜が始まるのである。
好奇心の塊の私は、麦ワラ帽子に網を被せてもらい叔父について行く。
叔父は巣箱の蓋を開け
「この大きいのが女王蜂で、そして、この白いのは次の女王蜂を作る為のローヤルゼリー。どうだ、試しに舐めてみるか?」と進められ舐めてみた。それは、子供の敏感な舌にはとても耐えられない不味であった。
そんな話しの中に、セイヨウミツバチの天敵の話しがあった。
「養蜂家の敵は、巣箱ごと壊してしまう熊と、巣箱の蜜蜂総てを短時間で食い殺してしまうスズメバチがいて、残念ながら今年も北海道でやられてしまった」と、悔しそうに話していた。
巣箱をバキバキと壊して蜜をペロペロ舐める熊。
そして、片っ端から蜜蜂をガブリガブリと食い殺していくスズメバチ。空想好きの小学生には十分すぎる程凄い話しであった。
また、幾度となく蜜蜂に刺されて泣きべそをかいていた私に「一番の長生きの職業はなんだか解るか・・・答えは養蜂家。少量のハチの毒は逆に体に良い。ロシアでは民間療法に取り入れられているくらいだから、少し位刺されても大丈夫じゃ」。
そんな幼少期を過ごしたせいなのか、ハチだと聞くといても立ってもいられないのである。
カメラ設定
絞り値:F/9、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:200、露出モード:マニュアル、露出補正:なし、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ピクチャースタイル:スタンダード、レンズ焦点距離:100mm
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用
使用機材
Canon EOS 30D、EF100mm f/2.8 Macro USM, SPEEDOLIHT 580EX 2灯使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
イチジクの花とコバチ2012.09.28
イチジクの花をご覧になった事がおありだろうか?
イチジクは漢語で書くと「無花果」。
「うん!?花が無いのか?」と、不思議い思われるのではないだろうか。
実は、壺状の形をした器官の内面に微小な花が多数密生した隠頭花序(いんとうかじょ)なので外からは見えないのです。外側から観察できないので、蝶などの虫達には気づいてもらえないのです。ならば、どうやって受粉するのだろうか?
イチジクとイチジクコバチの共進化について詳しくはコチラ
★「JT生命誌研究館」の研究紹介:昆虫と植物の共進化ラボ「生命誌32号」
http://www.brh.co.jp/seimeishi/journal/032/pdf/s32_202.pdf
東京都練馬区産のイチジクの実を割ってみた。覗き込むと、小さな黒い汚れのような物が付いている。もしや!と、急いでルーペで覗き込む。なんと、中には1ミリ強の小さな虫が5匹ほど入っていた。そいつらには翅が2対4枚あるのでハチ目の♀と思われる。そして、花の中で死んでいるのでこの花は雌花で間違いないだろう。しかし、日本の冬期の低温ではイチジクコバチは生きられないので、イチジクコバチではないということになるのだが・・・?
あとで聞いた話だが、「小学校の給食でイチジクがでたので、割ってみたらアリみたいな虫が5匹ほど入っていた・・・」。と善福寺公園のボート係の女性が教えてくれました。不思議、なんでコバチの数が5匹で一致するのだろうか?
カリフォルニア産のイチジクは日本へも輸入されているらしい。
カリフォルニアでは、イチジクコバチに受粉されたもののほうが甘くて美味しいといわれているらしいが、日本人には虫入りは受け入れられないだろうけれど。因みに、日本のイチジクはイチジクコバチの授粉を必要としない単為結果性品種なのだから入っていないはずであるけれど、練馬産のイチジクには入っていた事実をどう考えるか、悩みどころである。
東京都練馬区は都区内最高気温を今夏もたびたび記録していた地域のひとつである。近年は温暖化の進むこの地域でも奄美大島などに生息していたアカボシゴマダラや、インドやスリランカのワカケホンセイインコなどが野生化して沢山飛び交っている。
この時の撮影技法(ワーキングディスタンス)
レンズの先端から被写体迄の距離のことをワーキングディスタンス言う。よく勘違いするのが、カタログなどに書いてある「最短撮影距離」。これはカメラの撮像面から被写体迄の事をいう(レンズの最長時の長さ+マウントから撮像素子の長さを加える)。一般に売られているマクロレンズは倍率1xが標準なので、それ以上の倍率が必要ならばクローズアップレンズやエクステンションチューブなどのアクセサリーが必要になってくる。したがって、取り付けたアクセサリーでワーキングディスタンスが変わるのだ。
倍率が上がる弊害
1)被写界深度が浅くなる。
2)ライティングをコントロールすることが 困難になる。
3)近づきすぎて、虫などに警戒される。
今回のコバチ(1mm強)をCanonの(MP-E65mm f/2.8 1-5x)倍率5xで撮影するとなるとワーキングディスタンス(コバチとレンズ先端の距離)は40mmほどになりライティングが自由になりません。ちなみに、ニコンの60mmマクロレンズの最短は45mm、105mmマクロレンズならば148mmのワーキングディスタンスがありますから、105mmマクロレンズは60mmマクロレンズに比べ被写界深度が浅といえます。したがって、深い被写界深度が必要ならば60mm、長いワーキングディスタンスが必要ならば105mmと言う事になり、チョット悩ましいレンズチョイスになってしまいます。幸い、今回は動かない被写体だったのと、1mm強の小さな被写体だったので5xまで倍率が上げられるキャノンの特殊なマクロレンズMP-E65mm f/2.8 1-5xをチョイス、それにマクロリングライトMR-14EXを装着してバックライトにスピードライト580EXを一灯同調させて撮影しました。
カメラ設定
右上:Nikon D800, 絞り値:F/14、シャッタースピード:1/40秒,ISO感度設定:100、レンズ焦点距離60mm、露出モード:マニュアル、露出補正:−0.33、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、ROW。
左と右下:Canon 5DM2、絞り値:F/10、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:100、レンズ焦点距離65mmを5xで撮影、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、ROW。
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom4、最終調整:PhotoshopCS5使用
使用機材
上:Nikon D800、AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED、 ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11使用, LEDライト。SPEEDOLIHT SB-600をバックライトとして使用、三脚
下:Canon 5DM2, MP-E65mm f/2.8 1-5x 、マクロリングライトMR-14EX、SPEEDOLIHT 580EXをバックライトとして使用、三脚
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
カラスウリとエビガラスズメ2012.08.17
お盆が終わっても、茹だるような残暑の黄昏時。
白いドレスに盛装して怪しく闇に咲き乱れるカラスウリ。
レースに振りかけたパフィームを夜風に乗せて流すのだ。
闇に怪しく光る白いドレスと甘いフレグランスに誘われて、どこからともなくエビガラスズメがあらわれた。
軽いステップでホバリングを繰り返し、ご自慢の長〜い口吻で、カラスウリの甘いカクテルを次々に飲み干して行く。
それは、今宵カラスウリがエビガラスズメに、未来を託すために仕組んだ高等戦略が成就した瞬間でもあるのだ。
カラスウリ(烏瓜)ウリ科、つる性の多年草。
日没後19時頃に直径約7〜10㎝のレース状に広がり10分ほどで開花する。
午前2時を回ると次第にしぼみはじめ、翌朝には開花の姿を見る事は出来ない(キカラスウリは異なる)。
原産地は中国、日本。薮などにつるを絡ませて成長する。
カラスウリは雌雄異株で、花期は7〜9月。カラスウリの花筒は非常に長く、底に蜜をためるので、この写真に見るように、長い口吻を持ったスズメガでなければ花の奥の蜜を吸う事ができない。
また、夜間に目立つこの花は夜行性のガを呼び寄せるための誘導灯のようなもので、白いレースは他の虫達を止まらせない金網ブロックの役割をかねているとおもわれる。
しかるに、夜間ホバリングの出来るスズメガに特定した花粉媒介の高等戦略をとったとおもわれる。
このように特定の花と昆虫が依存し合う現象を「共進化」と呼ぶ。
写真上:雌花
写真下:雄花とエビガラスズメ
エビガラスズメ(蝦殻天蛾、学名: Agrius convolvuli)
チョウ目、スズメガ科。
翅の開張90~100mm。アメリカ大陸を除き、全世界に分布する。
太陽が沈むと花蜜を求めて飛び、長〜い口吻を伸ばして蜜を吸う。
昼に飛ぶ蝶と真逆の生態の夜行性のガである。
幼虫の食草はヒルガオ、アサガオ、サツマイモ、マメ科などのつる性植物。
日本では蛹で越冬して年二回、5〜6月と7〜9月出現する。
この時の撮影技法(三点が揃えば超ウルトラ級の撮影難度)
必須の機材はストロボとLEDライト。
「闇の中での撮影現場」「マクロレンズで捕らえる小さい被写体」「素早くチョコマカ動く被写体」この三点が揃えば超ウルトラ級の撮影難度です。
昼間のオオスカシバの吸蜜シーンの撮影もそれほど簡単ではないが、闇の中で素早く移動するエビガラスズメは小さくてピント合わせが非常に難しい。
それに、ライト光に敏感なエビガラスズメの吸蜜シーンのシャッターチャンスは運がよくて一回のみである。
さて、この難しいシーンを画にするにはどうするか?
何事にも言えますが、シミュレーション撮影を何回もトライする事につきるようです。
まず、撮りたい画の距離を想定し、LEDライトを左手に持ちターゲットのカラスウリの花をファインダーの真ん中におさめる練習を行う。
暗がりで素早く行えるようになったらしめたもの、半分は成功したようなものです。
あとは運を天にまかせてひたすら待つのみ。
いざ現れたら慌てず素早く間合いをつめ、思い描く画(長〜いストローが映る角度)を想像してカメラの角度を決め構える。
そして、もし貴方に運があればシャッターが押せるという塩梅です。ちなみに、今回は被写体との距離約30㎝、フルサイズ一眼レフカメラに60㎜マクロレンズ、この組み合わせは被写界深度も非常に浅く、F/14まで絞りこんでも約3㎝前後しかピントが合わないので「置きピン」での撮影は不可能です。
それに沢山のカラスウリの花の何処に現れるかを予測する事は不可能で三脚も役立たず。
合計この場所に3日間で5回ほど訪れましたが、4回はカメラの近くにも寄ってくれず・・・、あきらめかけた真夜中の2時30分頃やっと撮影に成功しました。
残念ながらこの時間帯は花のレースがしぼみ始めていたのがチョット残念。
カメラ設定
上下とも同じ:絞り値:F/14、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:200、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、ROW。
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom4、最終調整:PhotoshopCS5使用
使用機材
Nikon D800、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、 ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11使用, LEDライト。上のみSPEEDOLIHT SB-600をバックライトとして使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
金ボタル(ヒメボタル)2012.07.05
七夕の頃、漆黒の森の中で金色の光の矢を放つ小さなホタルが棲んでいる。そのホタルの名は、光の色から名付けられて「金ボタル」と呼ばれています。ゲンジボタルよりも点滅間隔がとても短く、キラキラとまるでイルミネーションのように輝くのです。
現地にはお昼に到着。
1日で撮れる画は一枚のみであるから、慎重に場所選びをする。
アクセスランプやモニターなど光の出るところは総て黒のテープで覆う。なぜならば、恋の邪魔になる光は総て御法度なのである。
総てを整えたならば、あとは漆黒の闇に踊る、恋の瞬きの瞬間をただひたすら待つのみだ。
夜の帳が降り
最初の金ボタルが、漆黒の森へ向け恋の矢を放った・・・。
金ボタル(和名でヒメボタル、学名はHOTARIA PARVULA KIESENWETTER)
陸生のホタルの1生態型。
昭和34年3月27日岡山県指定天然記念物に制定。
黄金の光を発する事からその名前「金ボタル」がつけられました。
森に棲み幼虫は、陸生の巻貝「オカチョウジガイやベッコウマイマイなど」を食べ成虫になる。
♀体長約6mm前後と小さく、後翅が退化しているので飛べない。
♂体長約8mm前後、飛翔は地表から約1m〜2mの高さを飛び♀とのフラッシュコミュニケーションを行う。
めでたく♀との交信が成立した♂は♀のところに降りて行き交尾をすませ、その後♂は灯りを消し静かにあの世へ旅立ちます。
見れる期間:岡山県新見市哲多町蚊家地区の天王八幡神社の社叢に発生した金ボタルのフラッシュコミュニケーションを見れる期間は7月の七夕を挟んで10日間ほど。
漆黒の森の中で、恋の矢を放つさまはまさに幻想的で必見です。
この時の撮影技法(金ボタルの撮影技法)
金ボタルはゲンジボタルよりも光がとても弱いので、明るいレンズで高感度設定が求められる撮影です。(※土日三脚禁止なので平日に行くべし)
ここ哲多町は日本一厳しいマナーが求められるひとつの場所でもあります。
イントロでも述べましたが、光の出るモニター、パイロットランプなどは総て黒テープで光が漏れないように塞ぐ事を求められます。
少しでも光が漏れると即刻退場です、また携帯電話も主電源を切っておかなければなりません。
複数枚のレイヤー合成を行う事を前提でカメラ設定。
撮影中はモニターで確認できないので、明るいうちに撮影場所を決め、三脚にセットしてピント合わせをしておく事。さらに、ピントが動かないようにテープで固定する。
森の中が薄暗くなり始めたならば、背景を一枚撮影しておく事。
金ボタルはゲンジボタルよりも発光が小さいので(ゲンジボタルの約1/3)ISO感度を1250に設定する。
レンズはF値の明るい標準レンズか広角レンズを選ぶ絞りは、F/1.4、シャッター時間30秒。
デジタルカメラは長時間露光が苦手なので30秒ごとに30分間シャッターを切り続け、パソコンにて複数枚のレイヤー合成を行うのだ。(この時はフイルムカメラも持参して、ネガフイルムのISO1600を装填。30分間の露光を行った。出来上がりの画はほぼ同じでした)
三脚、黒色のテープ、明るいレンズ、レリーズは必須です。
「万葉集」
蛍なす ほのかに聞きて・・・
カメラ設定
上:絞り値:F1.4、シャッタースピード:30秒,ISO感度設定:1250、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、16ビット
使用ソフト
Raw現像ソフト:Lightroom4、最終調整レイヤー合成:PhotoshopCS5使用
使用機材
Canon EOS-1Ds Mark II、Canon 50mm F1.4、三脚:HUSKY 3D、レリーズ、黒色のテープ、水準器。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家