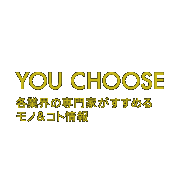- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
ターコイズグリーンに輝くミドリシジミ2014.06.23
早朝6時、秋ガ瀬公園に到着。何故だか早く着いたはずなのに気が急いていた。車のトランクからウェーダーを引っ張りだし、もんどりうって履き替える。果たして今朝は君に出会えるのか一抹の不安を覚えているのだ。何故なら、君の出現が早い年もあれば遅い年もあるから・・・。
例年、出現実績のあるハンノキ周りの開けた場所を探す。
ほどなく、B型、B型と続けて同じ形の♀が見つかるが、なかなか新鮮な♂が見つからず1時間ほど経過したその時。
「♂」登場!
それも、翅を開いている奇麗な個体が目の前2m程の距離に現れたのだ。
私はまるで獲物を捉えた猫みたいに、ソロ〜リとベストポジションへ水音も立てずに移動する。
鱗粉の向きが影響しているのであろうか?、頭側に回り込むと早朝の太陽光を受け翅表がよりゴージャスにターコイズグリーンに輝きを増している。
それは、徹夜明けの目には鮮やかすぎる美しさだ!
ミドリシジミ(緑小灰蝶、学名:Neozephyrus japonicus、アゲハチョウ上科、シジミチョウ科)
日本にはミドリシジミと名のつくシジミは13種。
この蝶も前々回の「ウラナアカミシジミ」とほぼ時を同じくして、梅雨時に現れるゼフィルスである。
日光を浴びると翅を広げ♂は写真のようにターコイズグリーンに輝く。
♀は翅表が、血液型と同じようにA型,B型,O型,AB型といる。
8時過ぎあたりから♂は樹上でテリトリーを張り、近づくものを追い払う。
そして夕刻になると黄昏飛翔が始まる。
幼虫はカバノキ科のハンノキやミヤマハンノキなどを食草とする。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「ベストポジション」
ターコイズグリーンの輝きがこの画の命と考える。15年程前になるだろうか一時期熱帯魚と水草にはまり、ディスカスを沢山育てていた。ブリリアントターコイズブルーやターコイズグリーンに輝くディスカスの色に引き込まれていたせいか、ミドリシジミのこの色がたまらなく好きなのである。
前回の「ウラナミアカシジミは翅裏」が美しく、今回の「ミドリシジミは翅表」がとても美しいと私は思っている。そう、あの時のディスカスの輝が蘇るのだ。
そこで、どの位置から狙ったら一番美しく輝くか、周りをぐるりと一周してベストポジションを探し出す。
やはり頭側からが目の覚めるようなターコイズグリーンに輝くので、その位置に移動して慎重にフォーカスを合わせ撮影した。
撮影自体はそれほど難しくは無いけれど、翅を広げたシーンに出会える確率はとても低く理想のポジションを確保しづらいから「☆☆☆」としておきましょうか。
無論、いる所にはいるのでしょうが東京近郊では生息数が少なく見つけるのが難しい。そんな数少ないチャンスを確実にものにするには長めの望遠レンズがオススメです。
その訳は、前後を奇麗にぼかし主役をより強調したいから。また、羽化したてはあまり敏感ではないので近づけるが、それ以外は敏感な個体もいるからです。
また、成虫はクリの花などの蜜を吸うがここではクリの樹がないので葉っぱの上の朝露などを吸う場面が時々見られるけれど、このような状態になると食事に忙しくなかなか翅を広げてくれないので、つい「早くお腹一杯になって広げてよ・・・」などとつぶやくのである。
カメラ設定
絞り値:F6.3、シャッタースピード:1/250秒,ISO感度設定:400、レンズ焦点距離280.0mm、露出モード:マニュアル、露出補正:-1/3、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:風景、Raw。
使用ソフト
PhotoshopCS6(Rawデータ現像に使用、トリミングあり、最終画像処理に使用)
使用機材
Canon EOS 5DMⅡ/EF70-200mm f/2.8L IS USM + EXTENDER EF1.4X
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
見事な狩り蜂の技(アケボノクモベッコウ)2014.06.16
自分の体よりも大きなハシリグモを、口、翅、6本足と体の全てを巧みに使いエアーボートのように水面を滑るように運ぶ狩り蜂がいる。
それは、腕利きの職人だけが魅せる見事な手さばきのような動きで、ただただうっとりと無駄の無い美しい動きに見入ってしまうのだ。
観察を続けなんとなく分かってきたのだが、どうやらお互いが水をはじく構造(細かな毛で表面積を増やし水素結合を味方につける)になっているらしい。
この狩り蜂は、その構造を巧みに利用する運搬方法あみだしたのだ。
後ろ足2本でハシリグモの足を写真のように保持し、中足で胴体を挟み込む、そして前足の2本はミズスマシのように表面張力を効かせる、さらに口で前足をくわえ翅を激しくはばたかせ波をけたててスィ〜ッ、と滑空するように高速で運ぶのである。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「スピード感を画にする」
遠くから波をけたてて運ぶスピード感こそがこの画のポイントであると考える。
そこで、波紋を味付けとしたいのでf/10にて波紋を脇役として強調した。
ポイントは2つ
① 高速シャッター:翅の羽ばたきがある程度分かるように1/800秒で撮る。羽ばたきは想像以上に早いので当然翅はぶれる事になるが、このぶれ加減が動きを表現出来るので悪くはない。悪くはないが翅脈をビシッと捉えたい欲望が沸き起こるのである。そこに写真の醍醐味のひとつが潜んでいるのではないかと考えている。翅脈を鮮明にと捉えるには『こぼれ話』へ。
②被写体が小さく運ぶスピードが早いのでピント合わせはとてもシビアだ。
3Dトラッキングでは小さくて動きが早いので効きにくいので、マニュアルフォーカスを選択。
被写体に近ずきすぎるとピント合わせが困難になるのである程度距離を開け小さく撮る。200mmの場合約2〜3m辺りに焦点をもってくると、被写界深度が稼げるという訳である。
現像時にトリミングを行う。
こぼれ話(高速閃光で翅の羽ばたきを完全に止めたい)
この狩り蜂の翅の動きを鮮明に写しとめるには1/10000秒以上が必要と思われる。
そこで、
シャッタースピード1/250秒にセット、ストロボの閃光時間の短さで止めるテストをした。
被写体までの距離約3m。高速閃光を得る為にGNの大きいニッシンのマシンガンストロボMG8000を2灯使用(理由は小さなコンパクトストロボでは光量が足りない)、FULL発光では閃光時間1/800なので発光量を1/128に絞ると閃光時間が1/20000〜1/30000あたりになるのでトライしてみたが、残念ながら肝心なアケボノクモベッコウが現れず時間切れとなった。
カメラ設定
Nikon D800, 絞り値:F10、シャッタースピード:1/800秒,ISO感度設定:800、レンズ焦点距離200mm、露出モード:マニュアル、露出補正:+0.33、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。
使用ソフト
SILKYPIX Developer Studio Pro 6(Rawデータ現像に使用)、PhotoshopCS6(トリミング/最終画像処理に使用)
使用機材
Nikon D800/VR 70-200mm F/4.0 G
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
雨宿り2014.06.10
もう3日間ほどシトシトと長雨が続いている。
夕刻、ふと「この雨の中どうしているのだろうか?」と気になってウラナミアカシジミに会いに出かけた。
この辺かな?とあたりをつけて探す。
ほどなく、美しく輝く姿をクワの茂みの中で見つけた。
「やっぱりここでしたか!」と冷静さを装いつつ葉っぱの間にレンズをそ〜っと滑り込ませ、
マニュアルフォーカスリングをくるくる回しフォーカスする・・・。
ス〜ッ、とファインダーに浮かび上がったウラナミアカシジミ、
想像以上に美しい!
息を止めスローシャッターで「カ〜シャ!カ〜シャ!カ〜シャ!」と3回程連写する。
ウラナミアカシジミ(裏波赤小灰蝶、学名Japonica saepestriataシジミチョウ科アカシジミ属)
日本には25種が生息。
ゼフィルス(Zephyrus)の一種で樹上性があり昼間は葉に止まりじっとしているが、夕方になると黄昏れ飛翔が見られる。ちなみにゼフィルスとはギリシャ神話の西風の神ゼピュロス(ヴィーナスの誕生の画の中で、ヴィーナスに風を吹きかける姿で描かれている)。
天候のことわざ『西風に雨は梅雨どきだけ』。まさに梅雨時に現れる蝶である。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「スローシャッターの極意」
雨のシットリ感が欲しくてレンズはLEICA 100mm Macro-Elmaritをセレクト。
難関が2つ。葉っぱの奥で雨宿りしているので、枝が邪魔になり三脚が使えない。イメージからストロボは使いたくない。ならば、と二通りのテクニックを使って撮影した。iso感度を上げ3枚連写を行うのである。iso1250まで感度を上げ露出を計るとシャッタースード1/25。ブレを押さえるには通常100㎜ではシャッタースピード1/100以上が必要と言われているが今回は1/25である。このレンズ、美しいボケ味と立体感はまさに一級品であるが、手ぶれ補正などついていない古い代物であるがゆえにブレには細心の注意が必要なのだ。そこで、カメラをしっかりホールドして、息を止め3枚ほど「カ〜シャ!カ〜シャ!カ〜シャ!」と連写する(理由は2枚目当たりからブレが少なくなる)。
味付けとして、クワの紅い果実、と雨の雫のバランスに注意しつつ構図とシャッターチャンスを決めた。
こぼれ話
高感度カメラが欲しい!
もうすぐニコンとキャノンから新機種の発表があるらしい。もし高感度に改善がみられれば購入したいと思っている。普段から「嘘八百」と仲間から言われるようにiso800をよく使うし、場合によっては800以上もガンガン使う。高感度こそがフィルム時代に味わえなかった最大の利点でもあり、今まで撮れなかったシーンが狙えるのだ。だったらそれを道具として使わない理由などどこにもないと考えている。多少ノイズが増えようが立体感にかけようがそんな些細な事は問題ではない。特殊な撮影をのぞき、撮りたいものをその現場の光源下で撮りたいのである。
チョット脇道へ
ロバート・キャパの『ノルマンデー上陸作戦』の写真を覚えておいでだろうか、命がけで撮影したフィルムを『LIFE』の暗室係の助手は興奮のあまりネガフィルムを乾かす際、加熱のためにフィルムのエマルジョン(乳剤)を溶かしてしまった(『LIFE』は11コマが使えたと言っている)。
キャパは命がけで撮った写真でありながらこの事を怒る事もなく、撮り終えた写真には全く執着しなかった。後に、「106枚うつした私の写真の中で救われたのは、たったの8枚きりだった」とキャパ自身が『ちょっとピンぼけ』ロバート・キャパ、川添浩史/井上清一訳の中に記している。
ピンボケで粒子が荒れていたが、それがより緊迫感を与えていた。
蘊蓄に富んだキャパの誓い
絶対禁止!
酒、賭博、爆撃照準機、女!!
ロバート・キャパは写真技術には無頓着で、金が入るとカメラ機材を買うよりも先ずスーツを新調した。
カメラ設定
絞り値:F2.8、シャッタースピード:1/25秒,露出モード:マニュアル、露出補正:−1/3段、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ISO感度設定:1250、ピクチャースタイル:風景
使用機材
Canon 5D MarkⅡ、LEICA 100mm f/2.8 APO-Macro-Elmarit-R、LR-EOSマウントアダプターにて取り付け
使用ソフト
Raw現像ソフト:最終調整PhotoshopCS6使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
本当に騙しだまされてきたのか?(シランとヒゲナガハナバチの共進化)2014.05.16
シランには花蜜がない(ランの花の多くは花蜜がない)。
本当に、花蜜というお駄賃を貰えない事に気づかずに今日までポリネーターとして来てしまったのか、あるいは定花性を何かの手違いでDNAに刷り込んでしまいボランティアを続けているのか?
その事が気になり、数えきれない程のシランの花の形状と香りを嗅いでみる。
やはり花蜜は見つからないけれど、薔薇のような甘い香りの中に腐ったような微香がある。
この香がヒゲナガハナバチの♀のホルモンと似ていたとするとならば、四六時中パトロールを繰り返す♂達の行動のひとつが理解できるのだが・・・。
しかし定花性で行動を説明するには不可解である。
謎解きの仮説をたてる。
シランの受粉もヒゲナガハナバチノの交尾も、開花のタイミングに合わせて速やかに達成しなければ、次世代へ強い遺伝子の命のバトンは渡せない事になる。
そこでシランは膨大なエネルギーを必要とする花密作らないことにして、
花の香りを送粉シンドロームとして進化させてきた。
唇弁もまたヒゲナガハナバチの着地に都合のいい形に整え、交尾中も滑り落ちないように柔らかな表情のギャザー状に仕立てヒゲナガハナバチを誘惑し共進化してきたのではなかろうか?と仮説をたててみる。
無論、
ポリネーターの指名に失敗した場合に備え、シランはバルブという保険もしっかりかけて抜かりは無い。
いっぽうヒゲナガハナバチは花蜜を貰えない事は重々承知しており、香りに刺激されたお仲間達に容易く出会える社交場のひとつとしてシランを利用してきた、と仮説をたててみる。
とすると無駄にアチコチ相手を探しまわらなくても良いし、最大の使命である子孫繁栄の行為に効率よくエネルギーを集中する事が出来る。
結果、巡り巡ってシランのポリネーターとして共進化してきたことで、子供達の未来を支える事となる。
ポリネーターの定花性はとりあえず様々な花から花蜜を得るとして、出会いの場所と花蜜場所を「区別できるように高等進化した」、と仮定したならばヒゲナガハナバチの謎のボランティア行動のひとつが氷解するのだが・・・。(ランとハナバチはもっとも進化したと言われている)
もしかしたら、
もっと古い時代の化石が新たに発見され、高等進化したランの花とハナバチを恐竜も見ていた・・・。などとたわいない仮説遊びに戯れるのである。
シランとヒゲナガハナバチの起源について、詳しくはコチラ
http://www.kosjp.com/reikai/r0907_t.html
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/6-8.html
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/shiran.html
写真解説
1:粘着性の高いシランの花粉。納豆みたいに良く伸びる。
2:花の中に潜り込み、中で回転出来ないため後ずさりで出てくる時にペタンと背中に花粉を背負わされた瞬間。
3:ムラサキツメクサで一晩過ごしたヒゲナガハナバチ。背負わされた花粉と朝露がついている。早朝5時撮影。
4:お尻を突き出すように後ずさりで出て来た♀に、♂達(2頭)が素早く飛び乗り交尾をとげる瞬間。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「インテリジェンス」
ポリネーターの定花性を仮説に沿って色々な場所を渡り歩き、時間帯や光の状態などによる変化をつぶさに観察する。シランの花の構造や、粘着性の高い花粉を背負わされてそのまま眠りにつく姿や、様々なシーンを目に焼き付けその先を自分の考えでインテリジェンスする。
カメラ設定
1:絞り値:F10、シャッタースピード:1/200秒,ISO感度設定:800、
2:絞り値:F11、シャッタースピード:1/640秒,ISO感度設定:800
3:絞り値:F16、シャッタースピード:1/20秒,ISO感度設定:800
4:絞り値:F11、シャッタースピード:1/1000秒,ISO感度設定:800
使用ソフト
PhotoshopCS6使用(Rawデータ現像にも使用)
使用機材
Nikon D800、①③④AF-S NIKKOR AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED、②AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED,
②④ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
山桜の幹から椿がニョキリ!?2014.03.31
絶妙なバランスの山桜と椿が存在する。
やるか、やられるか、それとも共生か、その事が気になって2年程この山桜と椿を見続けている。
会いに行くたびに空想遊びに迷い込む。
「どうしてこうなったのか?」たぶん山桜の株立ちの幹の間に椿の種が落ち発芽。
椿の根っこは素早く株立ちの間に滑り込ませ土まで到達せしめるが、山桜が大きく成長するとともに幹どうしがくっ付き合い幹からニョキリ状態になった。
椿の根はすでに菌根菌の菌糸ネットワークが築かれていて、情報や物質のやりとりでを行うことで病気や栄養不足を補う事ができた・・・。これから先、幹の固さは椿の方が固いだろうから山桜に絞め殺される事はまずないだろう・・・、などと至福の空想遊びに迷い込むのだ。(今のところ、どの椿とどの椿が交配したか分からず、残念ながら椿の名前は専門家でもわかっていません。昆虫か鳥のみぞ知るでしょうか?)
株立ちとはコチラ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024904175
図解の3で椿の種が株立ちの間に落ち発芽。素早く根を地中に届かせ、菌根菌の菌糸ネットワークが完成する。(写真のニョキリ状態は図解の4あたりに当たると思われる)
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「ストロボで主題を強調」
昼間の明るい光線状態で撮影すると、肝心な椿の幹の出所が分かりにくいのでストロボ3灯で主題がより強調されるようにライティングした。
カメラは三脚にセット。
ストロボは左右からと桜のバックに1灯セットして、総てのストロボにTOKISTAR 2.4Gワイヤレスセット:TS-824-M を付け同調した。
このワイヤレスセットは昼間の明るい場所でも少しぐらい隠れても離れてもすこぶる反応がよい。
また、マシンガンストロボは熱対策が施されており連続発光にとても強いので、車を使用出来ない時には今お気に入りの組み合わせとなっている。
狙い通り、このライティングで山桜の幹の凹凸と椿のニョキリ箇所を強調できたのではないだろうか。
カメラ設定
絞り値:F9、シャッタースピード:1/200秒,ISO感度設定:200、露出モード:マニュアル
焦点距離28.0 mm
使用ソフト
Raw現像ソフト:最終調整PhotoshopCS6使用
使用機材
NIKON D800、AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR、スピードライト:NISSINマシンガンストロボ「MG8000」3灯使用、TOKISTAR 2.4Gワイヤレスセット:TS-824-M 3台使用、アンブレラ使用、ハニカムグリッド、ライトスタンド、三脚
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家