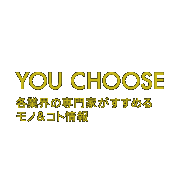- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
フタツバギングチバチ2015.08.10
目の前に小さなコバエのような物体がチョコマカと高速で飛んでいる。
細目でジロリンチョと動きを観察するとお腹に小さなヒメヨコバイを抱え、巣口にピュッと飛び込んでいく。早ッ!
—-
早速、2灯のストロボを使用して、HSS(ハイスピードシンクロ)撮影と普通のシンクロ撮影を2通り試してみたのだが・・・。
フタツバギングチバチ:ハチ目(学名:Crossocerus annulipes hokkaidoensis TSUNEKI,1954)
稀な種で詳しいことはほとんど分かっていない小型のギングチ。
体長:6〜7mm。獲物:ヨコバイ、キジラミ類。朽木に営巣する。
複数の個体が巣口を共有するのを目撃。
変温動物(狩バチ類ほとんどは変温動物)狩をしなくてはならないので丸型体型やフワフワの毛が生えていたら運動性のデメリットの方が大きいからではないかと思われる。ちなみにミツバチやハナバチ類は恒温動物。
参考文献
1)田仲義弘著 『狩蜂生態図鑑』P126,フタツバギングチバチ
2)改定埼玉県レッドデータブック2002http://153.150.68.50/BDDS/redlist/data/Crossocerusannulipeshokkaidoensis.html
3)変温動物、恒温動物詳しくはコチラ
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「飛翔シーンはダントツに難しい被写体のひとつ」
小さいハチゆえに超高速の動きと羽ばたきである(まるでコバエのような飛翔)。
この日の道具はCanon EOS7DMarkIIでトライしてみたが後悔する。
小さすぎて素早い。
ならば高解像度のカメラでトリミング前提での撮影がベストと考えCanon5DsR をチョイス。
写真:上
ストロボの出力を最小の1/128(閃光時間1/20000s)に、絞りF/8,1/8000s,ISO:3200に設定。
ヒメヨコバイを狩り巣口に飛び込む場面。これが思い描いた画に近いようである。
写真:下
ストロボの出力を2段ほど下げ1/32(閃光時間1/9000s)に、絞りF/10, 1/250s, ISO:400,ストロボ光量1/32では動きが早すぎて閃光時間内でもブレてしまう。ちなみに1/64では((閃光時間1/15000s)である。
Web用の小さなサイズの画面では分かりづらいが、よ〜く見ると羽は完全にブレ、体は微妙にブレているのがわかる。
ブレにシビアなCanon5DsR 5060万画像の解像度の凄さがわかろうというものだ。
ところで、
閃光時間には2つの異なる基準があることをご存知だろうか?
フラッシュ光は常に一定ではなく、t0.1総閃光時間とt0.5有効閃光時間がある。
すなわちストロボは光り始めて徐々に消えていくので、どこからどこまでが光っている時間かというのは、ほとんどのメーカーが数値を公表していないから厄介だ。
さらに難しくしているのは、メーカー、環境、距離、発光量、アクセサリーなどもろもろが影響しあうからさらに複雑で難しいのである。また、ストロボの出力量を変えると微妙に色温度が変わってしまう。
ムム、こればっかしは経験を積むしかないのだ・・・が、デジタルは現像時に色温度は変更可能だから考慮する必要なし。
撮影地:練馬区石神井公園
カメラ設定
2枚の設定は画像の中を参照:Canon 5DsR,レンズ焦点距離100mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw
使用ソフト
Photoshop Lightroom CC (Rawデータ現像)
Photoshop CC(最終画像処理、トリミング)
使用機材
Canon 5DsR, EF100mm f/2.8 Macro USM、Speedlight: Godox V860 C×2灯、旧型の「Sells II C」でHSSシンクロ、カメラはローアングル用三脚Fotopro fph-53pに装着、さらにETSUMIのクリップにSpeedlightを取り付けFotopro fph-53pにかませる、バックライトに後方斜め45度付近からSpeedlight:Godox V860 C1灯を三脚:VANGUARD VEO 265CBに装着、Canon リモートスイッチ RS-80N3
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
梅雨葵の花の中で雨宿り(シロオビキホリハナバチ)2015.07.09
雨の土曜日、
出かけようか・・・迷っていた。
絵柄はすでにシミュレーション出来ていたけれど。
—–そんな時には、
迷ったら出かける、あとあと後悔しないために。
シロオビキホリハナバチ(学名:Lithurge collaris)ハチ目、ハキリバチ科。
日本ではハキリバチ科は約54種。シロオビキホリアナバチ、シロスジキホリアナバチと混在するが、今回はシロオビハキリバチとする。大きさは約14mm。植物の葉を切り取り単房の壁や間仕切りなどの材料とする。巣房の中に花粉や蜜を集め幼虫の餌にする。大顎が発達していて、体色は黒い。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「季節感を写し込む」花はシットリとした雨の日ががよく似合う。
梅雨に入ると、立葵(別名:梅雨葵)、芙蓉、ムクゲが咲き出す。花期にリンクするように現れるシロオビキホリハナバチの季節感を一枚の画にしたかったので、雨のこの日に殊更こだわる。オシベにしっかり摑まり雨宿りをしている主役(シロオビキホリハナバチ)とふたつのアクセントの脇役(立葵の色と水滴のシズル感)バランスを考えハチは左斜め上に配置した。花と水滴を写し込む為にはある程度の引きが必要となり、主役はますます小さくなってしまうから精密なピント合わせを求められる。
花の見分けかた。
立葵、芙蓉、ムクゲは、いずれもフヨウの仲間。
「立葵」は草本、つまり草。オシベだけが目立ち、遅れてヒゲのようなメシベが出てくる。
「ムクゲとフヨウ」は木本、つまり樹木。ふたつの違いは、葉っぱを見れば分かりやすいです。芙蓉の葉っぱは5角形でムクゲは葉が小さく尖がっています。その他にもメシベを見れば分かります、5本に分かれて先端が曲がっていればフヨウ、曲がっていなければムクゲです。
撮影は簡単そうだが、
雨と風に揺れて、ピント合わせがとてもデリケートであるから撮影難度(☆☆)とした。
撮影地:シロオビキホリハナバチの♂/練馬区石神井公園B球場
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/160秒,ISO感度設定:800、レンズ焦点距離105mm、露出モード:マニュアル、露出補正:+1/3、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw 14bit。
使用ソフト
Photoshop Lightroom CC (Rawデータ現像)
Photoshop CC(最終画像処理、トリミング)
使用機材
Nikon D810,レンズ: AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、ワイヤレスレリーズ:Velbon TWINI R4N、三脚:VANGUARD VEO 265CB、
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
招かざるハラアカマルセイボウ2015.07.06
宝石のような
美しいドレスを纏った、ハラアカマルセイボウの♀が今回のソープオペラの主役です。このハチ、身なりは美しいが、前回のナミツチスガリ♀にとっては招かざる客(寄生蜂)である。
いよいよコハナバチ類の獲物で満杯になりかけた頃、タイミングよく現れて次々に卵を産み付けていくが、全てに産み付けるような不合理は決して行わない。
観察を続けて驚く
「どこに隠れて見張ろうか?」
「あそこの小石の陰に隠れたほうが良さそうだ・・・」
「帰ってきた〜、ソレッ!」
などと、まるで人がやりそうな行動をこの個体は演じるのだ。
画像解説
1、そろそろか?と卵で膨らんだお腹でパトロール飛行。
2、巣穴入り口付近の土に触覚を差し込み、伝わってくる振動で中の様子を探っていると思われる。
3、小石の上に登り、身を隠す場所を探す。
4、小石の陰に隠れ、ナミツチスガリの帰りを待つ。キターッ!
5、すかさずダッシュ、後を追うように巣穴に飛び込む。
6、無事産卵を済ませ、顔を泥だらけにして巣穴から出てくる。
ハラアカマルセイボウ
(学名:Hedychrum japonicum、ハチ目、セイボウ科)
大きさは約5〜8mm。分布:北海道、本州、九州。金属光沢がひときわ美しことから、宝石蜂(Jewel-wasp)とも呼ばれている。ツチスガリ類の巣に入り込み寄生する。すなわち、この画では宿主のナミツチスガリの幼虫を食べて育つ捕食寄生である。
参考文献
田仲義弘著 『狩蜂生態図鑑』
(7日間通ったうち、1日だけ田仲氏の生態解説をお聞きしながらの実に贅沢な撮影でした)
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「主役を小さく撮る意味とは」
寄りではなく引きの画面構成で、主役は一枚を除きすべて小さく写す。すると、見た人は単純な絵柄の中から動きのある小さな一点に集中し、次はどこへ移動し何をするのか?などと想像の世界に入り込む。今回の画に限って言うと、組写真で小さく配置しているからこそ得られる効果で、実物よりも大きすぎて画面いっぱいの寄りでは想像力を掻き立てないのではないかと思うのです。
撮影難度
何日も通い続ける体力と根気を必要とするので☆☆星とした。
カメラ設定
6枚とも同じ設定:Canon EOS7DMarkII, 絞り値:F9.0、シャッタースピード:1/2000秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離(35mm換算)160mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw
使用ソフト
Photoshop Lightroom CC (Rawデータ現像)
Photoshop CC(最終画像処理、文字入れ、トリミング)
使用機材
Canon EOS7DMarkII, EF100mm f/2.8 Macro USM、三脚:VANGUARD VEO 265CB、Canon リモートスイッチ RS-80N3
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ハチの驚くべき羽ばたき回数(ナミツチスガリ)2015.06.14
この4枚の写真は、ナミツチスガリがコハナバチを狩り地中に掘った巣に持ち帰ってきた場面です。
それにしても凄い羽ばたき回数で、普段通りに撮影してしまったら翅が消え失せて写ってしまうのだ。
それが、当たり前と思考を止めてしまったら面白くない。
「完全に止める」か、それとも「好みのブレ加減に演出する」か?
そのためには、最低何万分の一が必要か!?
思い描く画作りのために、ハチの羽ばたき回数を徹底的に調べあげた。
ナミツチスガリ(学名:Cerceris hortivaga、ハチ目、フシダカバチ科)
ハチがハチを狩る、狩りバチである。獲物はコハナバチ、ヒメコハナバチ類。地中に多房巣を作る。
分布は北海道から九州。
体長は12〜15mm。ちなみに他の働き蜂はニホンミツバチの10〜13mm、セイヨウミツバチは12〜14mm。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
ミツバチの羽ばたきは恐ろしく早く一秒間、一往復約250回と言われています。
したがって片道は計算上約500回になるので、完全に翅の動きを止めるには1/50000秒が必要、と単純計算ではなります(ナミツチスガリはセイヨウミツバチの働き蜂とほぼ同じ大きさ)が、この計算は一往復の平均値を割り出したにすぎません。
それに小さな獲物だと、触覚を大顎で咥えお腹とお腹を密着させ空気抵抗を抑え飛翔運搬するのだが、いろいろな個体を観察した結果、獲物(写真4)が大物ならば密着度や重さが起因し羽ばたき回数も物理的に異なる事になる。
従って、獲物の大小、初速、中間、終点では当然スピードは異なる。
この4枚の撮影結果を見比べると、片道の中間地点辺り(写真3.4)のマックススピードはおそらく約1/100000秒〜1/500000秒が必要と思われる。
う〜む、1/20000秒前後ではまったく歯が立たないことに唖然とする。
ところで、一眼レフデジタルカメラのX同調速度は1/8000秒が限界。
Canon EOS7DMarkIIも最高シャッタースピードは1/8000秒が限界である。
さて足りないシャッタースピードをどうするか?
答えは日中シンクロでFP発光(ハイスピードシンクロ=以後HSSで統一)を行う。
そう、クリップオンタイプのストロボ発光量の出力を絞ればよいのです。
今回は最小の1/128に絞りましたが、それでも約1/20000秒前後。片道の中間地点(写真3.4)では羽ばたきスピードがマックスになるので当然翅はブレてしまいます。
動きのある画が好みならコレでOKですが、上記の事を理解していなければ、好みの翅のブレ加減を演出できないという事になります。
すなわち、晴天下のマックスでの中間地点では(1/50000秒以下)、翅の痕跡が失われている可能性が大となる計算になります。
しかし、往復の切り替え点(写真1.2)ならば一瞬止まるポイントがあるので光量1/128前後に絞れば、このように翅の動きを止める事が出来るのです。
この日は晴れ。
EOS7DMarkIIの限界のシャッタースピード1/8000秒に設定。ISO:1250で絞りf11にすると、カメラの露出計ではアンダー3絞り程になるので、当然ハチは光量不足でかなり暗く映る。
そこでHSSでストロボを適正露出に設定(ハチとの距離:20cm程に設置)して焚くと、約1/20000秒以上になる計算なので、往復の切り替え点でタイミングが合えば、翅がある程度止まって(写真:1.2)映るというわけです。
ちなみに(写真:1)は一灯のみ前方上から俯瞰ぎみに発光。(写真:2〜4)は3灯使用しHSSを行った。
羽ばたきの回数、詳しくはコチラ
http://www.athome-academy.jp/archive/engineering_chemistry/0000000157_all.html
カメラ設定
4枚とも同じ設定:Canon EOS7DMarkII, 絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/8000秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離(35mm換算)160mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw
使用ソフト
Photoshop CC 使用(Rawデータ現像、トリミングあり)
使用機材
Canon EOS7DMarkII, EF100mm f/2.8 Macro USM、(写真2〜4)はSpeedlight: Godox V860 C×3灯、旧型の「Sells II C」でHSSシンクロ、斜め左上45度1灯をローアングル用三脚Fotopro fph-53pに装着、バックライトに後方から1灯VANGUARD VEO 265CBに装着:地面に直接1灯置いて使用、お手製座布団:カメラを乗せ地面すれすれに設定、Canon リモートスイッチ RS-80N3
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ジョウビタキをHSSで撮る2015.03.16
逆光に映える白髪頭のジョウビタキ♂にお互い親近感を覚えつつ、何日か撮影に通い詰めた。
より美しい飛翔の瞬間を捉えることが出来ないかとあれこれと思案する。
たどり着いたのは、10枚連射で1/8000秒のハイスピードシンクロ(HSS)でピタリと止める。
そこから、イメージした画作りを考えるのがデジタル一眼レフの醍醐味のひとつでもあり、フイルム時代には味わえなかった面白さでもあるのだ。
ジョウビタキ(尉鶲、常鶲、学名:Phoenicurus auroreus Pallas)
スズメ目、ツグミ科。冬鳥としてチベット、中国などから日本全国に渡来する。
大きさはスズメよりも少しだけ小さい。
食性は昆虫類やクモ類、ピラカンサなどの実。
開けた環境を好み、それぞれ縄張りをもち単独でいる。
ジョウビタキのジョウは「尉」で銀髪のこと、ビタキは「火焚き」で火打ち石をたたく時の音に似た鳴き声をする事からヒタキ。人をあまり恐れない、愛嬌のあるアイドル的な冬鳥である。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「HSS 1/8000秒の世界」
逆光の中、ジョウビタキの羽が美しく透けて羽の一枚一枚がクッキリと写っている飛翔の場面が撮りたくて、10枚連写で1/8000秒のハイスピードシンクロ(HSS)を行った。
何故ストロボを焚いたかというと、理由はふたつほどある。
逆光でジョウビタキの美しい羽色が暗くくすむのが嫌であったのと、斜め前方45度付近からストロボを焚き立体感を出す。ただし、ストロボ光が強すぎては台無しなので、出力はチョットだけ抑えめにする。
目標が決まれば、あとは必要な道具をチョイスするだけ・・・。
送信機「Sells II C」の新型を購入したが、Canon EOS7DMarkIIと相性が悪く使えない。う〜む、どうしたものかと他を探すと、旧型の「Sells II C」が見事HSSした。
使用したスピードライトGodox V860 Cは中国製ながらリチュウムイオンバッテリーなのでチャージが早く10枚連射にもついてくる優れものだ。値段も純正の約1/3。
お願いとお知らせ
息子(裕介)が郷土芸能に魅せられ、全国を巡り撮りためています。
そして、いよいよこの秋に写真集を上梓することになりました。
なかなか見応えある力作です。
是非下記のURLにアクセスいただき、応援して頂ければ親としてこのうえない喜びです。
クラウドファンディング
https://greenfunding.jp/lab/projects/1030-
カメラ設定
Canon EOS7DMarkII, 絞り値:F4.0、シャッタースピード:1/8000秒,ISO感度設定:3200、レンズ焦点距離135mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw
使用ソフト
PhotoshopCS6使用(Rawデータ現像、トリミングあり)
使用機材
Canon EOS7DMarkII, EF70-200mm f/4L USM、Speedlight:Godox V860C+受信機付き1灯、マンフロット 1005BAC ライトスタンド、ラジオスレーブ:送信機Sells II(旧型) 、三脚:GITZOマウンテニア2型4段GT2542、レリーズCANON REMOTE SWITCH RS-80N3使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家