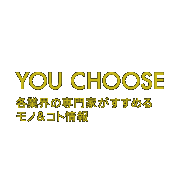- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
キイロスズメバチの狩りの一場面2016.10.04
蟄虫(すごもりのむし)戸をとざすころ
このキイロスズメバチはニホンミツバチの巣口で狩りをしていた。見かけはとっても怖そうなお顔なれど、慣れとは恐ろしいもので、このお顔に正対してもちっとも怖くないのです。むしろそのフォルムとカラー配色の見事さに心揺さぶられ、吐息が漏れてしまうほど・・・。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「閃光時間1/40000sの世界」
翅脈がクッキリと見えた画が欲しくて、高速閃光のストロボのひとつであるNikon SB-700の出力を下げ、M1/128(閃光時間1/40000s)の最小出力、最速閃光に設定しました。キイロスズメバチぐらいの大きさになると、羽ばたきの中間地点を切り取っても、1/40000sではご覧の通り翅もピタリと止まるのです。理論上、キイロスズメバチの1秒間1往復の羽ばたき回数は200回以下、片道では400回以下ということになります。すなわち、「ストロボの閃光時間」と「被写体のスピード」を把握できると、ブレ幅の加減を思いのままに操る事が可能となるのです。言うまでもなく、把握するにはトライ&エラーの地道な積み重ね検証が必要になります。
撮影地:東京都練馬区石神井公園
お知らせ
「ナショナルジオグラフィック」10月号P16〜P23
“写真は語る民俗芸能に見た日本の心”
西村裕介の特集が組まれています。興味のある方は書店でめくって見てください。
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/200秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離200mm、露出モード:マニュアル、露出補正:−1、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。Nikon SB-700 約1/40000秒(M1/128)
使用ソフト
PhotoshopCC2015.5.1使用(Rawデータ現像+トリミング)
使用機材
Nikon D810, AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、Nikon SB-700
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
一瞬、ルリボシヤンマと目があう!?2016.08.26
処暑、福島県のデコ平湿原へ向かった。
ゴンドラ駅山頂に降り立つ、空は青く心地よい涼風がそよいでいる。
逸る気持ちで改札を抜けると、眼前にヨツバヒヨドリの群生が広がっていて、そこには当たり前のようにアサギマダラが乱舞しているのだ。
飽きるほどアサギマダラを撮影し、興奮を鎮めつつ湿地帯の方に下る。そこには、木道がありエゾリンドウなどの花々にレンズを向けつつゆっくりと移動。
—-突如、木道上で寒冷な気候を好む、ルリボシヤンマと鉢合わせしたのです。
私は瞬時に歩みを止め、じっくりと観察を始める。体近くをすり抜けるその時、複眼が鮮やかな青緑色であることを確認。どうやら成熟した♂で、♀を探してのパトロール中のようである。
周りはとても静かです。
シャッター音に反応したか、一瞬だけルリボシヤンマと目があった。・・・ように感じられたのだが。
トンボでも目があうと、ドキッと摩訶不思議な感覚に捕らわれます。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「トンボの美しい飛翔シーンを前方から狙う」
素早く不規則に動く被写体を、前方から焦点距離200㎜、絞りF4.5(ほぼ解放で背景を綺麗にぼかしルリボシヤンマだけにピントを合わせる)で狙うには、まぐれの要素を含むピント合わせが求められる。毎度の事ながら水平移動ならば簡単なのだが・・・。「目があってドキッとした」思いを画に収めたくて、あえて正面からのアングルに挑戦。
さて、どうするか? 観察を続けた結果、このルリボシヤンマほんの一瞬だけホバリングをおこなう瞬間があるのに気付き、その一瞬のチャンスを狙うこととした。さらに、トンボ独特の翅の形状をしっかりと綺麗に見せたいがために、翅のブレを嫌いシャッタースピードは高速の1/1000sに設定。
撮影地:福島県デコ平湿原
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F4.5、シャッタースピード:1/1000秒,ISO感度設定:200、レンズ焦点距離200mm、露出モード:マニュアル、フォーカスモード:MF、露出補正:+0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。
使用ソフト
PhotoshopCC2015.5使用(Rawデータ現像+トリミング)
使用機材
Nikon D810, AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
美しいナミハンミョウの狩り2016.07.26
昼、鹿児島市で用を済ませ空港へ向かう。途中で加治木町の霧島市よりの端っこに「一番ラーメン」があり、いつも常連客で繁盛している。ここで、お昼に食べるのは鹿児島ラーメンではなく、いつも決まってチャンポンなのだ。よくよく考えてみれば他のものを食したことがない。
熱々のチャンポンが運ばれてくると、綺麗に整頓された調味料置きから、すりおろしニンニクをたっぷりと投げ入れ、チャンポン専用の三杯酢を4周ほどかけ回し食らうのである。
吹き出す汗と格闘しながら、鹿児島発ANA628便の出発にはまだ2時間ほどの余裕がある。
「さ〜て、何処に行こうか。藺牟田池には昨日行ったしな〜」と記憶の地図を広げモグモグ。やっぱり通い慣れたところが良かろうと、約10分で行ける龍門滝に決めた。道すがら、お土産用に「新道屋」の加治木まんじゅうを10個買う。いつも「本日は終了いたしました」の看板を目にして、ちくしょうと引き返すのだが、今日はなんだか運が良いぞとハンドルが軽い。—–ピュッッと到着。
山道脇のシラス堆積岩では僅かに水が染み出ているので、目的の甲虫と出会える確率が高い、ここで時間が許す限り粘ることにした。背中で滝の爆音を聞きながら、次々に現れるアシナガバチや蝶などと戯れていると、目の覚めるようなナミハンミョウ登場である。うれしさを噛み殺し、私は少し離れた所から様子を窺う。何やら獲物を探しているようである、ならば多少時間がかかろうが私は粘りますよ・・・と、1時間ほど経過、こうなりゃ我慢比べです。ほとんど動かないナミハンミョウから、チョットでも目を切れば、たちどころに行方知れずとなりかねず凝視し続けるのですが、この日は梅雨が明けたかのようなピーカン。こりゃー堪らんばい、と日陰に隠れるが南国の容赦ない強烈な暑さに汗たら〜り。ヘナヘナと気力が萎えかけた頃、突然ナミハンミョウは獲物を見つけたか、猛ダッシュしたのだ。私はベストポジションへ、そろ〜りと移動。スローモションは歯痒いけれど、急に動くと気付かれてアウトですからね。
爆音とニイニイゼミの鳴き声にかき消されつつ、連写!
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「狩りをするまで粘る」
ナミハンミョウは甲虫の中でもタマムシと並んで、一二を争う美しさですが、こちらは獰猛な肉食。できれば、狩りの場面を、大あご強調で前方から撮る。そのためには時間の許す限り粘ると決めたのです。
ターゲットと方針を決めたら、近づけるのか近付けないか判断が必要です。今回のナミハンミョウは、あまり近づきすぎても逃げられてしまうのではないかと考え、望遠ズームレンズを使用することとしました。日陰で動きが俊敏なので内蔵ストロボを明るくなりすぎないようにアンダー(-0,67)に強制発光。個体差にもよるがナミハンミョウは以外と臆病で用心深いようです。この狩りでも反撃を受けそうになると、素早く離れ、隙を見て再アタックを続けていましたが、獲物が大きすぎたのか、最後はとうとう諦めて去って行きました。残念ならが、獲物の名前が不明。もしかして、噛まれて丸くなるのでヤスデの一種だろうか。でもね〜、なんだかドイツ菓子のプレッツェルに似ているようで、チョット美味そうに見えませんか・・・。
撮影地:鹿児島県姶良郡加治木町・龍門滝近く
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/160秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離200mm、フォーカスモード:MF、露出モード:マニュアル、露出補正:-0,67、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。
使用ソフト
PhotoshopCC2015.5使用(Rawデータ現像+トリミング)
使用機材
Nikon D810, AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、内蔵ストロボ強制発光
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
クビワギングチの狩り2016.07.12
昨夜、シミュレーションを済ませておいたので機材のチョイスは完璧である。
しかし、この日はやけに蒸し暑いので、重たい機材を携えて出かける事に少しばかり躊躇していた。だが、晴天ならばハチに出会える確率が上がるので、サングラスをかけオープンカーで出撃した。(アシスト自転車)
クソ暑いのに、汗かきかき、コギコギ。狙いは蛾類成虫を主に狩るクビワギングチである。
先客のT氏は、すでに下段の方の巣口にセッティングを済ませ、私と入れ替わるように背後の「ツミの餌渡し」の方に移動された。これ幸いと、T氏よりも上段の巣口にセット。程なくグッドタイミングで自分の体よりも大きなハマキガ?を狩った、クビワギングチが上段の方に戻ってきたのです。
「バシャ!バシャ!」
NIKON D810がハイスピードシンクロ(1/8000s)で唸ります。
このシャッター音に気づき、背後からT氏が大慌てで駆け戻ってこられる気配が・・・。
「ワオ〜獲物がデカイ!」
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「裏技」
クビワギングチは体長約8mm。狩る獲物は、ヤガ、ヒメハマキ、ハマキガ、ツトガなどであるらしいが、生態は未だよく分かっていないらしい。このギングチはトチノキの朽木に穴を開け営巣していた。ちぃちゃくて素早い飛翔で、狩りから戻ると躊躇なく、ピョンと巣に飛び込む。被写界深度は数ミリで、ジャスピンはまぐれの要素を含む難易度である。
そこで、「裏技」仕掛けが必要となる。巣口にティッシュなどを詰めて、ピョンと簡単に飛び込めなくする。しめしめ、これで複数回のトライが繰り返されることになる。
ここからが肝ポイント。前もって置きピンの位置決めを済ませておくが、その方法はいたって簡単。侵入角度を予測し飛翔方向入り口に、ピント合わせ用の手頃な物を潜入角度に合わせて置く。この状態を維持しつつ、好みの角度位置にカメラをセットすれば置きピン完了。さらに、愛嬌ある顔を狙って少しだけ前方から狙う事にしたので、これで、ジャスピンの難易度が数段上がる事となる。何故ならば、侵入角度がカメラと水平ではなくなるので、ジャスピンは交差する所の1点のみ。すなわち“神の領域”まぐれとなる。
翅ブレの演出は、ストロボの出力を2段ほど下げ、M1/32(閃光時間1/9000s)セット。できれば出力をもっと下げて、M1/128(閃光時間1/20000s)ブレ幅を小さくしたいところだが、ニッシンMG8000 マシンガンストロボはハイスピードシンクロ時(シャッタースピード1/8000s)では設計上、たとえマニュアルであってもM1/128に設定できない仕様なので(シャッタースピード1/320s以下ならば出力M1/128も可)、仕方なくシャッタースピード1/8000sで出力をM1/32とした。さらに、背景を真黒に落としたくなかったので、ISO感度を1250にし背景の緑を取り入れる事とした。
さて、羽ばたき回数をミツバチに置き換えて推測してみよう。1秒間1往復約250回、片道は計算上約500回となるが、クビワギングチは狩バチで大きな獲物も運ばなければならない、さらにミツバチよりも小さい。という事は物理的に羽ばたき回数はもっと多くなると考えられる。したがって、完全に翅の動きを止めるには閃光時間1/50000s以上が必要、と単純計算ではなるけれど、羽ばたきの片道の中間地点ではもっと早くなるはずで、シミュレーションでは、1/100000s前後が必要となる。これ以下だと、閃光時間内に翅の移動幅が大きくなりブレが増すと言う理屈です。
また、晴天下でシャッタースピード1/320s以下ならば、中間地点に限って、閃光時間内にかなり移動するので、翅の形跡はほとんど写らない計算になるのです。ただし、撮影環境が暗所で露出アンダー2ぐらいならば、閃光時間優先で最小の出力、M1/128にセット出来るので、シャッタースピード1/320s又は1/250 s(カメラメーカーにより異なる)以下は、たとえ1秒だろうが、スローシャッターによるブレを考慮する必要はほとんど無いと考えても良いでしょう。
ちなみに、
閃光最速のひとつは、これか?ニコン SB-700は約1/40000秒(M1/128) メーカー発表値。
撮影地:練馬区石神井公園
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F10.0、シャッタースピード:1/8000秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離105mm、ファーカスモード:MF、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。
使用ソフト
PhotoshopCC2015.5使用(Rawデータ現像+トリミング)
使用機材
Nikon D810, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、スピードライト:NISSINマシンガンストロボ「MG8000」1灯使用、外部電源にパワーパック P5.8使用、Yongnuo製 YN-622N ニコン専用 i-TTL対応 ラジオスレーブ/ワイヤレスフラッシュトリガー使用、カメラ用三脚:GITZOマウンテニア2型4段GT2542、スピードライト用三脚:VANGUARD VEO 265CB、ピンセットとティッシュ(巣の入り口を塞ぐために使用)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
梅雨の後期に咲く花(半夏生)2016.07.05
夏至から数えて11日目あたり、エコトーンに半夏生(ハンゲショウ)の花が咲き始めると、いよいよ梅雨明けの頃あいとなる。
半夏生のフェノロジーは実に趣味深い。
6月、花序近くの葉っぱが白く化粧を始める頃、花穂が立ちあがり、7月に入ると梅雨の終わりを告げる、ちっちゃな白い花が咲き始めます。
この花には蜜はないけれど、花粉を食べにハナアブの仲間やハムシ達が訪れます。
そして、その虫たちを狩るカリバチやカマキリなどが集まってくるのです。
この日は、35℃越えの猛暑日
知り合いが「もう梅雨明けしたんじゃないのかい」と、うんざり顔でつぶやいています。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「五月晴れの日を狙って」
よく目にするのは、キヒゲアシブトハナアブ。エコトーンに生息する虫としては最適と考え、このハナアブを狙うことにしました。
主役(主題)の半夏生の特徴である白化現象のコントラストをひときわ強調できるように、五月晴れの日を選び、背景は暗くなる場所に咲いている花をセレクト。
あとは脇役がピッタリとおさまる構図に飛び込んでくるタイミングを図ることにしました。
カメラ設定はこのことを踏まえシャッタースピード:1/400秒が最低限必要と決め、フォーカスはMF(マニュアルフォーカスに設定)。
撮影地:練馬区石神井公園
カメラ設定
Nikon D810, 絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/400秒,ISO感度設定:800、レンズ焦点距離105mm、フォーカスモード:MF、露出モード:マニュアル、露出補正:+0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:スタンダード、Raw。
使用ソフト
PhotoshopCC2015.5使用(Rawデータ現像)
使用機材
Nikon D810, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家