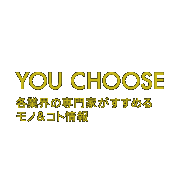- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
4年振り東京大雪2018.01.24
10時頃から降り出した雪は17時になってもやむ気配なし。携帯メールに、明日の仕事は雪のため延期と知らせが来ていた。画像処理やらスケジュール調整などを済ませ、TVで相撲を観戦。高安が仕切りを始めた頃、外に出て様子を見ると、あっという間に車も門柱も20センチ越えの雪化粧になっていた。軍配がかえり「手にカメラを持って!」行司の掛け声が聞こえたかのように、写欲全開のスイッチが入る。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「逆光で雪を強調する」
ストロボをライトスタンドに取り付け、そのストロボが見えないように門柱の背後に隠しスレーブで同調。すると、逆光で雪が強調され何気ない雪景色がドラマチックに浮かび上がるのです。
「設定の肝」
まず始めに背景の露出をどの位にするか最初に決めなくてはいけません。今回はISO感度を1000に設定し背景を露出アンダーに決めた。導き出された露光は1/6秒の絞り8、ストロボをマニュアル1/1に設定してフル発光。当然、ストロボの当たった所の雪は閃光時間が短いのでピタリと止まります。
撮影地:東京都西東京市 自宅
カメラ設定
NikonD850, 絞り値:F8、シャッタースピード:1/6秒,ISO感度設定:1000、レンズ焦点距離18mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ピクチャーコントロール:A オート、14bitRaw、ストロボ発光:光量1/1
使用ソフト
PhotoshopCC19.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
NikonD850、16.0-35.0 mm f/4. VR、ストロボ:GODOX V850、スレーブ使用:GODOX433MHz、ライトスタンド:Manfrotto NanoPole Stand MS0490A
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
年の始めのえべっさん2018.01.18
「♪商売繁盛で笹持ってこい!年の始めのえべっさん♪」
若い女性の威勢のいいお囃子が鳴り響き、釣られるように福笹を手にした参拝者は狙いの福娘に縁起物を授けてもらい、商売繁盛♪。ここの10日戎に選ばれし福娘は才色兼備の18〜23才(高校生除く)の未婚の女性。履歴書に福娘経験者と書けば縁起を担ぐ大企業などに引く手あまたとか。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
10日、大阪での仕事が思ったよりも早く終わったのでタクシーで「今宮戎神社」へ向かうも、凄い混雑である。この様な人混みでは出来るだけ軽装が鉄則なのですが、コインロッカーも見当たらずローラーキャスター付きカメラバックとライトスタンドを担ぎ、「堪忍でっせ〜」という気持ちで飛び込んでいった。出来るだけご迷惑にならない様に、ノーファインダーでパパッと撮影。
「スナップショットの極意はノーファインダー」
学生の頃、スナップショットの名手アンリ・カルティエ=ブレッソンは露出、距離などの設定はカメラを一切みる事なく瞬時に動かす練習を重ね、人に気付かれる前に撮影していた事を知り、私も密かに練習を重ねました。すると露出計、撮影距離などノーファインダーでどれだけフォーカスリングを回せば良いのか体が覚えてしまうので、あとは被写体に集中するだけと言う塩梅です。神の使いである巫女さん達は、肖像権なしと説明会で告げられているので、撮影にはとても協力的で笑顔を振りまいてくれます。
1)人混みでは手動でのピント合わせが鉄則です、AFに任せではどこにピントが合うか分かりません。
2)画角は主役を活かす構図に合わせて事前に選びます。
3)ISO感度は大体の平均を計算に入れ今回はISO感度800に固定。
4)露出モードはオートで問題なし、今回は絞り優先。
撮影地:大阪府大阪市浪速区恵美須西一丁目 今宮戎神社
カメラ設定
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, AF:手動、ISO感度設定:800固定、露出モード:絞り優先オート、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:Natural,Raw
使用ソフト
PhotoshopCC19.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
スカイツリーとスーパームーン2018.01.09
1月2日は連れと「浅草演芸ホール」へ。アゴがおかしくなりかけた18:30分あたりで寄席を出て、すぐ斜め前の「まるごとにっぽん」へ夕食に行く。正月なのに野党の身では仕方あるまい、イタメシとワインでお腹をなだめ何気なく火照った身体を覚そうと4Fのテラスに出た。ふと、浅草寺の方角に目をやると低い位置に大きな赤い月が・・・。
アッ!
1月2日は「スーパームーン」
小さなバックにはE-M1 Mark IIに万能レンズの12-100mm F4.0 IS PROが付いている。直ぐに押上を目指す。狙いはスカイツリーの天辺にちょこんと乗ったスーパームーン。幸い、連れも撮影に目覚めたみたいで嫌がらずに積極的について来てくれるのでありがたい。
「私の方がセンスあるんじゃない?」
とかるいツッコミを受け流しつつ、絶景ポイントにエスコートするのです。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
狙いを明確にする
狙いの場所を探し当てるのが、今回最大のポイントのひとつでもあるが、ここには何回も通っているので大体の撮影ポイント、すなわち景色が想像できるので難なくクリア。1月2日のイルミネーションのカラーは縁起の良い「幟:のぼり」、3色が3日のローテーションで変わるので何時撮ったか大体予想出来るのです。それと、ちょっとした意外なヒントをひとつお教えいたします。それは出来るだけスカイツリーの天辺と月が接触するぐらいで撮影する事、後でズルしたんじゃない?なんて疑われたりしませんね。笑
手持ちでISO感度1250まで上げ難なく一発撮影。
豆知識
1)当然、これだけスカイツリーに近づくと月はとても小さく写り、スカイツリーにピントを合わせると月は当然ボケますが、絞りを絞ることにより月の”光条(光芒)”が美しくなります。
2)反対に、スカイツリーから20〜40キロほど離れると望遠レンズの圧縮効果で月を大きく写せ、ある程度両方にピントがきます。
3)予想以上に月の動きは早いので、狙った位置に月を配置するには、多少の前後左右に動けるスペースが必要です。
撮影地:東京都墨田区押上 撮影時間21:32:30
カメラ設定
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, 絞り値:F7.1、シャッタースピード:1/10秒,ISO感度設定:1250、レンズ焦点距離23mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:Natural,Raw
使用ソフト
PhotoshopCC19.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ゆか紅葉(ISO感度25600の世界)2017.12.03
仕事で大阪に向かっていたが、ピークの紅葉を撮りたくて京都で途中下車した。
京都駅からバスに揺られ、南禅寺を目指していると車窓にポツリポツリと小雨、これも一興。薄暮のころ南禅寺に到着、観光客も少なめで一時境内をブラブラ。
—–流石にありきたりの紅葉写真に飽きてきたころ、南禅院の入り口に立って居た。感応に導かれ、拝観料を支払い門をくぐると、不図「ゆか紅葉」が目に飛び込んできた。
まさに、幽玄閑寂。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
画素数4575万画でありながら、高感度にめっぽう強い最新のNikonD850。
レンズは70-200mmf/4.0VR、光のとぼしい時間帯ゆえ、ISO感度を常用感度域の25600まで上げる。
ゆか紅葉を強調するために、つま先立、頭上に掲げてチルト式モニターで構図を確認しつつ、至極不安定な撮影スタイルを強いられながらのレリーズ(三脚はご法度)。今までの常識では撮影を躊躇してしまう条件下ながら、吐き出される画にはカメラブレほとんど無しである。撮影難易度は鼻歌交じりの星1つ。
すごいぞNikon!
撮影地:京都「南禅寺の南禅院にて」
カメラ設定
NikonD850, 絞り値:F7.1、シャッタースピード:1/100秒,ISO感度設定:25600、レンズ焦点距離110mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ピクチャーコントロール:A オート、14bitRaw
使用ソフト
PhotoshopCC19.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
NikonD850、70-200mmf/4.0VR
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
アブラゼミ 無防備のはずが2017.09.24
そのうちアブラゼミの交尾シーンには出会えるだろと、たかをくくって真剣に探さなかった。そのせいなのかはたまた運がなかったのか随分と歳月を要した。白露、東京都東久留米市の南沢湧水群へ、樹液の出ているクヌギを確認に行く。スズメバチ、カナブン、ルリタテハ・・・。特に変わったこともなく、ゆっくりと歩を進めていると仄暗い道の真ん中にアブラゼミが何頭か落ちていた。だが大抵はスズメバチなどに食われて頭なしの胴体空っぽである。それにしても、今日はずいぶん沢山の死骸が転がっているなと思いつつ近づき眺めてみた。 えっ、動いている・・・?!
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「思いがけない出来事に保険をかける」
全く予期していなかったアブラゼミの交尾シーンに出会えたのです。でも、繋がったまま歩いているアブラゼミの場所は仄暗く、ファインダーを覗くと、1/25sのスローシャッターです。長年思い続けたシーンにやっと出会えたのだから、そりゃ〜冷静では要られません! そう、虫好きの方ならわかると思うけれど、大抵の虫たちは交尾中はとても無防備。多少触ろうが突こうがまず大丈夫なのですが・・・。
でも、経験から下駄を履くまで何が起きるか分かりません。そこで、取り敢えず3枚連射の保険をかけるのです。これで、高鳴る鼓動を押さえ込んだので急ぎ広角レンズに付け替え、ISO感度などをいじっていたら、その時アブラゼミは進行方向の落ち葉に触れ、枯葉がひっくり返った拍子で、ぶったまげ離れてしまったのです。 ジィ〜! ああぁ〜!
撮影地:東久留米市 南沢湧水群
カメラ設定
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, 絞り値:F5.6、シャッタースピード:1/25秒,ISO感度設定:400、レンズ焦点距離120mm、露出モード:マニュアル、露出補正:±0、ホワイトバランス:オート、ピクチャースタイル:ピクチャースタイル:Natural,Raw
使用ソフト
PhotoshopCC2017.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M.60mm F2.8 Macro
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家