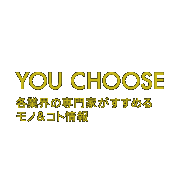- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
サトセナガアナバチは麻酔の名手2019.06.04
ひょっとしたら、宝石のようなサトセナガアナバチに出会えるのではないかと武蔵野中央公園の堆肥置き場に立ち寄った。その囲いは20センチ角の古材で囲われており、サトセナガアナバチの狩場には最適と睨んだのです、すでに6頭ほどが忙しなく獲物を探しているようである。私は鵜匠の気分「早く捕まえておいで・・・」。待つこと30分ほど、いきなりゾンビ化したクロゴキブリを引っ張り出して来ました。
何故、クロゴキブリは大人しく引っ張られていくのでしょうか?それは、麻酔医も驚く麻酔名人なのです。1回目の刺撃で、胸部神経節に麻酔薬を注入し、足の動きを弱らせ、次に脳内の逃避反射を司る部位へ正確に2回目の麻酔注射。これで、おとなしくなったクロゴキブリの触覚を半分ほど切り落とし、おおあごで触覚の根っこを咥えて「こっちおいで」と引っ張ると、垂直の壁をおとなしく歩いていくのです。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「斜光を利用して立体的に質感を捉える」
瞬時に、理想的な斜光により精妙な陰影が投影されるのでは、と想像しその場所に至るまで連写しました。陰影はとても重要なファクター、画に奥行き、立体感、質感を醸し出します。併せて、サトセナガアナバチ、クロゴキブリ、切り取られた触覚、大顎、すべてにフォーカスを合わせる事が重要と考えます。そのためには、被写体と撮像素子を平行にする事で、絞りF6.3でも狙った被写体部分にピントが合うのです。一見簡単そうですが、これらを瞬時に判断実行せねばならないので撮影難易度:星3としました。
撮影地:東京都武蔵野市八幡町2丁目4 (武蔵野中央公園内の堆肥置き場)
カメラ設定
絞り値:F6.3、シャッタースピード:1/400秒。ISO感度設定:1250。レンズ焦点距離60mm、35mm換算120mm。露出モード:絞り優先Aモード。露出補正:-0.3、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2019.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M.60mm F2.8 Macro
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
馬に喰わせるほどの・・・2019.05.22
4月〜5月に入ると、花、風景、鳥、虫(主に蜂)などの写真が、馬に喰わせるほどHDに溜まってきます。小出しも面倒だし、心にのこった、愛すべき虫たちのシーンを一部公開。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
左上から時計回り
上段左と上段右
ジガバチと尺取り虫。ジガバチ(腹部第1.2節が良く見えないため、ミカドジガバチ,サトジガバチこれかな?、ヤマジガバチの3択、固定に自信無し)とします。花の撮影途中ながら、ジカバチの動きに?!
尺取り虫のフンの臭いを嗅ぎ分けたか!後を追うと、尺取り虫を見つけ出し、ブスリと麻酔注射のシーンに遭遇。咄嗟のことで、ジガバチから視線を切ると見失うので、花の撮影設定のまま・・・。
撮影地:東京都調布市深大寺(神代植物公園:椿・さざんか園近く)
カメラ設定
絞り値:F4.5、シャッタースピード:1/250秒。ISO感度設定:800。レンズ焦点距離150mm、35mm換算300mm。露出モード:絞り優先。露出補正:±0、ホワイトバランス:オート
OLYMPUS M. 40-150mm f/2.8 PRO
右中段右下段
藺牟田池のベッコウトンボです。撮影のキーポイントは2つ、生息環境を取り入れるために背景の池が入るベッコウトンボを探す。それと、ベッコウ色を纏った羽化直後の未成熟個体の翅がキラキラ耀く瞬間を狙う。ベッコウトンボは環境省のレッドデータブックで絶滅危惧1類に指定。
撮影地:薩摩川内市祁答院町藺牟田(藺牟田池県立自然公園 ベッコウトンボ生息地保護区)
カメラ設定
絞り値:F9.0、シャッタースピード:1/400秒。ISO感度設定:400。レンズ焦点距離150mm、35mm換算300mm。露出モード:絞り優先。露出補正:±0、ホワイトバランス:オート
OLYMPUS M. 40-150mm f/2.8 PRO
カメラ設定
絞り値:F6.3、シャッタースピード:1/640秒。ISO感度設定:200。レンズ焦点距離150mm、35mm換算300mm。露出モード:絞り優先。露出補正:±0、ホワイトバランス:オート
OLYMPUS M. 40-150mm f/2.8 PRO
左下段
持久戦の様相から三脚とストロボ使用。ヒメコンボウヤセバチがメンハナバチの営巣穴を、じっと身じろぎもせず監視していました。そこにメンハナバチが帰ってくると、翅を小刻に震わせながらそっと近づいている場面です。翅に陽が当っていたので、ストロボ使用でも小刻みな翅の動きを低速シャッターにて表現。
メンハナバチが現われると、なぜ小刻みに翅を振るわせるのだろうか?何か意味があるはず・・・。
撮影地:東京都練馬区石神井台(石神井公園)
カメラ設定
絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/30秒。ISO感度設定:200。レンズ焦点距離60mm、35mm換算120mm。露出モード:絞り優先。露出補正:±0、ホワイトバランス:オート
ストロボ使用:Nissin ニッシンデジタル i40 、三脚:VANGUARD VEO 265CB
OLYMPUS M.60mm F2.8 Macro
左中段
ハバチ科(オオシロオビクロハバチ?)としますが、ヒゲナガハバチ亜科の仲間は属も多く絞込み困難、未固定お手上げです。沢山のオス達が群れていたので、この交尾シーンを想定し長時間粘り撮影。
撮影地:鹿児島県霧島市清水
カメラ設定
絞り値:F6.3、シャッタースピード:1/200秒。ISO感度設定:1600。レンズ焦点距離100mm、35mm換算200mm。露出モード:絞り優先。露出補正:±0、ホワイトバランス:オート
OLYMPUS M.12-100mm F4.0 IS PRO
使用ソフト
PhotoshopCC2019.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
こぶしの花が咲いた2019.05.08
4月26日気温6℃。
支笏湖の453号線でハンドルを握っていると、予期したかのようにこの風景に出会いました。寒々とした風景の中に、こぶしの花がポッと遅い春を告げるかのように咲いていたのです。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「一本のこぶしと樹々のアクセント」
南国生まれの私には、こぶし咲く北国の春の風景に密かな憧れを抱いていた。もし、推論したような墨絵の風景に出会えたならば、モノクロームで攻めようと決めていたのです。イメージ先行ながら主役のこぶし一本だけ中央下に配置し、アクセントに荒々しい樹々をシンプルに入れ込む。絞りは、樹々全体に被写界深度が得られる、絞り値F8.0に設定。
撮影地:北海道千歳市支笏湖温泉番外地
カメラ設定
絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/160秒。ISO感度設定:200。レンズ焦点距離75mm、35mm換算150mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-0.7、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2019.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M. 12-100mm f/4 PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
姫路城にレンブラント光線2019.04.04
貞和(じょうわ1345-1350)〜令和(れいわ2019〜)、築城は貞和2年(1346年)。
673年間で76回目の元号を重ねる、国宝・姫路城である。別名「白鷺城(はくろじょう・白漆喰)、鷺山(さぎやま・姫山には桜が多く咲いていた)」などと推論あり。4月2日、姫路での仕事が終わり、半年ほど前にロケハンした撮影ポイントへ直行するも天気悪し。こんな事もあろうかと前日に撮影プランABCの3本の矢を準備。残念ながらABの矢は折れちゃったけれど。—-暫くすると、黒い雲の切れ目から、ハイコントラストのレンブラント光線の矢が放たれた・・・。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「複数のプランをたてる」
野外では天候に左右される事から、あらかじめ撮影プランを2〜3パターン程考えておくことが肝心です。例えば、「晴れ、曇、雨天」ならば・・・などと。
A案、晴れならば、夜桜と城とベテルギウス。雲が多くてボツ。(5F屋上は18時閉鎖なので、3Fからガラス越しの予定だった)
B案、桜が満開ならば、鷺山へのオマージュから、城と桜。開花が遅れてボツ。
C案、色を排除して、城の美と畏れを、ハイコントラストの白黒写真でGO。
撮影地:兵庫県姫路市本町68 イーグレ姫路(屋上展望フロア5階)
カメラ設定
絞り値:F4.5、シャッタースピード:1/60秒。ISO感度設定:200。レンズ焦点距離44mm、35mm換算88mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-0.7、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2019.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M. 12-100mm f/4 IS PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
星降る夜の山桜2019.03.15
3月13日、鹿児島の山桜はすでに満開であつた。深更の雨も止み、快晴の下で撮影していたが、ふと!
春宵一刻値千金。—-月明かりに浮かび上がる、山桜と星の光跡を狙ったら面白いのではないかと閃いた。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆☆)」
「ライブコンポジット撮影」
星の光跡が刻々と伸びていく状況を、リアルタイムでモニターに映し出されるのがライブコンポジット撮影である。夜の帳が下り「快晴、雲無し、無風」と撮影条件は揃ったが、三日月のため光量が乏しく、山桜を白く浮かび上がらせる為に、ISOを高感度の1250、シャッター速度8秒に設定し1回撮影。これで、ライブコンポジットの準備が整い、4秒露光で約1時間、シャッター回数900枚程重ね合わせた。車の中で1時間ほど待機したので気付きませんでしたが、流れ星か国際宇宙ステーションISS、もしくは飛行機(離着陸の航路から外れているからISSか流れ星が濃厚)が横切り、その光跡が画面右上横にクロス、予期せぬ物語が生まれたようです。さらに、恒星の表面温度(K)の影響で、青(30000~50000K)、白(6000~7500K)、黄色(5300~6000K)、赤(3000〜4000K)、と色鮮やかに光跡で彩られました。
撮影地:鹿児島県霧島市国分木原
カメラ設定
絞り値:F4.5、シャッタースピード:1回目8秒露光で準備完了。ISO感度設定:1250。レンズ焦点距離40mm、35mm換算80mm。露出モード:マニュアル・ライブコンポジット4秒毎に約900回露光で1時間。露出補正:±0、ホワイトバランス:蛍光灯
使用ソフト
PhotoshopCC2019.0.0使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUSのOM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M. 12-40mm f/2.8 PRO
三脚:GITZOマウンテニア2型4段GT2542, 雲台: Really Right StuffのBH-40 Mid-Size Ballhead
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家