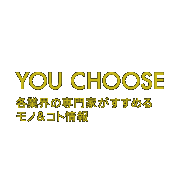- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
車窓から冬の日本海2020.01.20
冬、列車の車窓から日本海に張り付くような家並みがチラチラ見え始めると何故だか忘我状態になってしまうのです。この日も仕事を終え、富山駅から北陸新幹線に乗り込み、東京行き左側の窓側を確保する。素早くカメラの設定を済ませると、間も無くトンネルを抜け糸魚川付近である・・・。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「北陸の日本海をイメージ色に仕上げる」
冬の日本海のイメージ色を再現したくて、現像時にホワイトバランスの色温度を2900に設定。さらに、冬の厳しさを案じするかの様に、水平線を右傾きにして水平垂直を崩し、かつノイズを加え粒子を荒く加工。
撮影地:新潟県糸魚川市付近(かがやき:走行中撮影)
カメラ設定
絞り値:F8.0、シャッタースピード:1/5000秒、ISO感度設定:3200、レンズ焦点距離70mm、露出モード:M、露出補正:-1、ホワイトバランス:オート・現像時ホワイトバランスの色温度を2900に変換
使用ソフト
PhotoshopCC2020使用(Rawデータ現像)
使用機材
NIKON D850 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
今夜のお宿は迎賓館赤坂離宮2020.01.08
前庭にてライトなカベルネ・フランを飲みながら日暮を待っていた。外灯の明かりが灯る頃、足元で餌を啄ばんでいた仲良し雀が連れ立って飛び立った。ねぐらかな?後を追うと、この隙間に通い慣れた様子でチェックインいたしました。冬ぶくれ「ふくらすずめ・福来雀」は豊かさ繁栄の縁起物です。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「色温度とホワイトバランス」
色温度とは光の持つさまざまな色を表す指標で、単位はK(ケルビン)。太陽光なら5000K〜6000K辺りで、夕陽は2000K前後でしょうか、色温度が低いと赤く、高いと青く見えます。悩ましい事に、カメラのホワイトバランス調整は逆になるのです。数値が低いと青く、高いと赤く、真逆になるのです。なぜ逆なのか?(カメラのホワイトバランスは反対の色を足す事により、色被りした白を、自然な白に再現していると考える)。この事を踏まえ、後で現像出来るRawデータならば、画像ソフトのPhotoShopなどでホワイトバランスのスライドを前後させる事により、青く寒い冬ならば数値を低く、赤く暖かな夕焼けならば高く設定する事により、その時に感じた記憶色を蘇らせる事ができるのです。
今回は上:7650K、色被り補正+27。下:色温度7550K、色被り補正-10で現像し、その時に感じた暖かな夕陽感を記憶色としてイメージしました。それと、このレンズの手ぶれ補正の威力はすざましく35mm換算200mm、手持ちでシャッター速度¼でもブレなしの撮影が可能なのです。
撮影地:東京都港区元赤坂2-1-1 (迎賓館赤坂離宮)
カメラ設定
上:絞り値:F9.0、シャッタースピード:1/50秒。ISO感度設定:1250。レンズ焦点距離35mm、35mm換算70mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-2.0、ホワイトバランス:オート
現像にて色温度7650Kに変換、色被り補正+27に変換
下:絞り値:F9.0、シャッタースピード:1/4秒。ISO感度設定:1250。レンズ焦点距離100mm、35mm換算200mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-0.3、ホワイトバランス:オート
現像にて色温度7550K、色被り補正-10に変換
使用ソフト
PhotoshopCC2020使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M.12-100mm F4.0 IS PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
キチジョウソウ(吉祥草)2019.12.29
陰地にひっそりと咲くキチジョウソウ。うっかり見逃しそうなユリ科の小さな花(花は直径約1cm、花茎5〜13cm)です。この花が庭に咲くとその家に吉事があるとか。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆☆)」
「超広角レンズで花を強調する」
キチジョウソウの花を強調したくて超広角レンズをチョイスしました。根際から生える葉が邪魔するので超広角レンズを花にくっつくほど近づけて狙いました。そこにアクセントとして太陽の光芒を美しく入れ込むために絞りはF11に設定。このレンズの絞り羽枚数は7の奇数なので絞り込むことにより、倍数の14の光の筋が現れます。偶数の絞り羽枚数8ならば、光の筋は8しか現れません。ただし最新の高級レンズでは自然なボケ味を求める傾向にあり、絞り羽が真円になるように作られており、美しい光芒をあまり期待できません。もし、オールドレンズをお持ちなら一度試してみる価値大です。
撮影地:東京都練馬区石神井町5-17 (石神井公園:石神井城址碑近く)
カメラ設定
絞り値:F11、シャッタースピード:1/5秒。ISO感度設定:800。レンズ焦点距離9mm、35mm換算18mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-0.3、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2020使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO、ローアングル用三脚Fotopro M-5 MINI、OLYMPUS REMOTE CABLE RM-CB2使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
2番ホームから福山城2019.12.11
福山駅の新幹線ホームから望める超お手軽な、城撮影ポイントである。特に素晴らしいのは、新幹線2番ホームから窓ガラスを開放して撮影できるのだ。左側は伏見櫓、右側は筋金御門(どちらも重要文化財)、天守閣(真ん中に小さく見える)は昭和20年の福山大空襲により焼失復元。
福山城横のホテルにチェックイン後、プラリとお城へ。入り口付近には縁起物のクロガネモチ(苦労がなく金持ち)が結構沢山植えられていて、“こりゃいいね、肖りたい!”パチリである。城内にはそのまま入らず、門の手前で右側に回り込むと、やにわに鮮やかなサザンカの落花が目に飛び込んできた。雲の流れをよみ、天守閣を背景に超広角レンズにチェンジ。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「光を味方に」
上:快晴の下、お城の白い外壁と青空のコントラスト素晴らしく、天守閣が真ん中に収まる位置を探して、ホームをうろうろ。
下:雲の間からの太陽の強い光は避け、柔らかい光が差し込む時を少しだけ待ちサザンカの優しい色合いを求める。
撮影地:広島県福山市丸之内1丁目8 福山城
カメラ設定
上:絞り値:F9、シャッタースピード:1/500秒、ISO感度設定:100、レンズ焦点距離38mm、露出モード:マニュアル、露出補正:+0.33、ホワイトバランス:オート
下:絞り値:F10、シャッタースピード:1/250秒、ISO感度設定:800、レンズ焦点距離18mm、露出モード:マニュアル、露出補正:-0.3、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2020使用(Rawデータ現像)
使用機材
上:NIKON D850 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
下:NIKON D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
立冬の浄瑠璃寺と猫2019.11.24
11月8日、立冬の浄瑠璃寺にいた。
ひだまりで、黒猫と白猫が微睡。猫たちの足元には色付いたばかりの柿の葉の落ち葉が掃き溜められ、その隣には紫のコンギクが盛りとばかりに咲いていた。ちょっとばかし見上げると、縁起ものの南天の赤い実が重たそうに垂れ。さらにその背後上部にはオレンジ色の柿の実が今にもこぼれ落ちそうに実っていた。
——暫時は見惚れ、ここに雀でも居たならばコンプリートなのだが、まてよ、もしここに来年の干支のネズミがチョロリと現れたなら、騙された悔しさで・・・などと稚拙な妄想で眺めていた。その時、背後から“ジャバジャバ”と和尚が水を汲む音がした。流石である、微睡んでいたはずの猫たちは決してその音を聞き漏らすことなく、おもむろに背のびし、欠伸し、気怠そうに、のそっと水を飲みに行ってしまった。
この時の撮影技法「撮影難易度3星表記(☆)」
「立冬の役者のそろい踏み」
と、私は思ったのだが・・・。何処からか“凡俗だよね”と言われそうで甚だ心細い気持ちにもなるのだが、まあ良とする。狙いは、広角レンズを使用し、画面いっぱいに季節感を満載する。味付けに猫たちの僅かな動きで緊張感を表現。
撮影地:京都府木津川市加茂町西小札場40(浄瑠璃寺)
カメラ設定
絞り値:F7.1、シャッタースピード:1/200秒。ISO感度設定:400。レンズ焦点距離15mm、35mm換算30mm。露出モード:マニュアル。露出補正:-13、ホワイトバランス:オート
使用ソフト
PhotoshopCC2020使用(Rawデータ現像)
使用機材
OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II, OLYMPUS M. 12-100mm f/4 PRO
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家