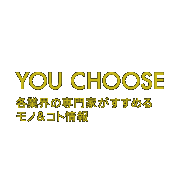- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄
フォトグラファー
- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-
ムラサキシジミの日向ぼっこ2010.01.04
アラカシの樹にムラサキシジミの巣があり、イロハモミジから僅か3メートル程の所にある。
正午の時刻になるとイロハモミジにサンサンと日が当たる。・・・ということは、この真っ赤なイロハモミジの上で日向ぼっこをするのでは、と鮮やかな配色のイメージをふくらませた。
果たして、気温があがり鮮やかな青紫色を輝かせヒラヒラとムラサキシジミは舞い上がり、イメージ通りにふわりと真っ赤なステージに舞い降りた。
ムラサキシジミ(紫小灰蝶)
チョウ目・シジミチョウ科に属するチョウの一種。
日本では本州から沖縄まで分布しており成虫で越冬。大きさは開帳時で約3~4㎝、表の翅は青紫色の鮮やかな色で黒褐色の縁取りがありとても美しいチョウです。翅を閉じる周りに溶け込むように、こげ茶色の目立たない翅色になり探すのは困難になる。
この時の撮影技法
今回は、「色により露出補正が必要」というお話しです。例えばスキー場などで雪景色を入れて、人を撮ると雪はグレーに、顔は黒く写ってしまい悔しい思いをされた経験は誰にでも一度や二度あると思いますが、何故こんな事が起きるのでしょうか?
それは、ほとんどのカメラの露出計はグレー(反射率18%)を基準値として作られているために、
白色はグレーに、黒色もグレーに露出補正されてしまいます。したがって、オート露出で撮影を行うと白いはずの雪がグレーに写ってしまうことになります。これを避けるひとつの方法として露出補正があります。雪の白さを出すには条件にもよりますが約1~2絞りほどオーバーに露光補正を行います。
今回の写真の場合、オート露出で撮ると深みのある赤いモミジも明るく写ってしまい台無しです。そこで本来の深みの赤を再現するために約2/3絞りほどアンダーに露出補正を行いました。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/180秒,絞りF5.6、ISO200。
使用機材
Canon EOS 30D ,300mm+1.4テレコン使用
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
雲上のバス2009.12.07
ここは立山の弥陀ヶ原からクネクネ道を5分ほど下山した辺りである。
先ほどまで初冠雪の紅葉に酔いしれていた私は、
まるで火照った心を冷ますように最終下山バスに乗り込んだ。
疾走するバスの車窓からは、真っ赤なナナカマドが後方に飛び去り、
天空は紅葉からの色渡しを待ち焦がれたように、
厳粛に夕方のマジックアワーが幕を開けた。
立山
山地の総称で、大汝山、雄山、富士ノ折立の3000メートル級の3つの峰を
現在は立山と称することが多い。
今回は立山ケーブルカーと立山高原バスを乗り継ぎ
標高2350メートルの室堂まで直接バスで行く。
この時の撮影技法
ブレを抑えるにはシャッタースピードを速く設定することが肝心ですが、
当然被写体、撮影環境、表現方法によりシャッタースピードの限界は異なります。
例えば、舞台撮影の場合、
暗い舞台での役者の激しい動きを止めるにはチョットしたコツがあります。
それは激しい動きの中にも一瞬動きが止まる瞬間が必ずあります。
その一瞬を見極めてシャッターを切るわけです。
当然、疾走するバスにもブレの少ない瞬間が必ずありそこを見極める事こそが一番のキモです。
今回は、跳ね上がった頂点の一瞬が一番ブレの少ない瞬間だったので、
そこを狙いシャッターを切り続けました。
それと、ブレ止めの隠し技として走る向きと逆方向へ一瞬レンズを振り撮影しました。
手ぶれ補正レンズの話
以前、夕刻の頃、
揺れる吊り橋の上からニコンの24~120mmVRレンズ(手ぶれ補正レンズ)を取り付け、
恐る恐るシャッタースピード1/8秒で撮影したことがある。
流石に吊り橋の上では無理かろうと思ったのだが、帰宅後モニターを見て驚いた。
見事にブレを抑えていたのである。
当時、Nikonは手ブレ防止効果3段分と公表していたが、
これは控えめな数字で実際は4段分の補正があるように思えたのである。
今回のクネクネ道を疾走するバスの揺れも相当なものだが(カメラブレと被写体ブレの合体)、
鼻歌交じりでブレを克服出来るとふんだのです。
カメラメーカーは違っても、
躊躇していた手持ち撮影でも手ぶれ補正レンズ付ならば
易々とシャッターが切れてしまう世界が広がってきたのです。
ただし、限度はお忘れなく・・・。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/1000秒,絞りF6.7、ISO400。
使用機材
Canon EOS 30D、24~105mmISズームレンズ(40ミリで使用)。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
紅葉はじめ2009.11.25
秋風が彩りを運んでくる頃、虫たちを探しに近場のフィールドへ出掛けた。
木の葉を揺らす風も少し肌寒いためか、
虫たちの姿もめっきり少なくなった公園をプラリプラリと探索していると、
赤く色づきはじめたイロハモミジが目に留まった。
控えめな紅葉はじめをしばし眺め、
明日はあのカメラで挑んでみるのもいいかな・・・、と、
思案しながら再び虫たちを探しに歩きはじめた。
この時の撮影技法
「秋のはじめ」の味わいを出すために一番気を遣ったのは背景の佇まいです。
主役を際だたせるための背景はとても重要で、
なかでも光の強弱がキーポイントだと思っています。
苔の生えた幹のしっとりとした質感、
そして画の左端に遠景を少しだけ取り入れて、
明るい光のアクセントで「秋のはじまり」感を表現してみました。
隠し味として低速シャッター(1/4秒)で葉っぱをぶらし、
心地よい空間を表現してみましたが如何でしょうか?
有名な紅葉名所だけではなく、
身近な場所でじっくりと時間をかけて独り占め出来る空間を見つけ出すことこそ、
写真撮影の醍醐味のひとつではないでしょうか。
解像度の話
このデジタルバック(CCD解像度3900万画素、有効画素数7216×5412ピクセル)は
高細密な画像データが得られ大伸ばし時にその威力を発揮します。
デジタル一眼レフタイプ(2000万画素クラス)より撮像素子が一回り大きいので、
その圧倒的な情報量がもたらす質感描写はさらに一段高いレベルにあろといえます。
今回の写真もモニターで拡大して見ると「オッ!」と声を発するほど葉っぱの一枚一枚見事に再現され、
その豊かな階調の美しさに感動すら覚えてしまいます。
ただし、ご存じのとおりモニターの解像度は72dpiで表示されるため、
この写真の大きさ(72dpi,20cm×15cm)まで縮小してしまうと、
その良さをモニターでは確認出来ないのは残念ですが。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/4秒,絞りF22、ISO100。
使用機材
Mamiya RZ67 PROⅡD、M140mmレンズ,デジタルバックPHASE ONE P45+,Gitzo大型三脚、レリーズ。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
山水(称名滝と紅葉)2009.11.13
この場所に着いたのは午後4時を少し回っていて、
称名滝が雨でボンヤリと浮かびあがっていた。
暫くすると薄暮の柔らかな光が紅葉をよりいっそう艶かに色づけして浮かびあがってきた。
私はこの時間帯の妖艶な光がたまらなく好きで、
この一瞬のためにひたすら待ち受けるのである。
狙いは神宿る山水。
称名滝
富山県中新川群立山町にあり、
立山連峰を源流とする滝で日本最大落差(350m)を誇り「日本の滝百選」に入る。
この時の撮影技法
霧雨と瀑布の水しぶきでカメラはずぶ濡れ状態になるので、
カメラを守るビニール袋、タオルなどが必須です。
薄暮の時間帯は光の陰影や色温度などが複雑に絡み合い刻々と表情が変化します。
その一瞬一瞬で閃いたイメージを如何に具現化するかがポイントです。
この時はスローシャッターで滝の流れを表現したかったので三脚を使用。
ビニール越しで構図を決めたらレリーズの直前にレンズの覆いをはずします。
露光中は水しぶきが架かるので何度もレンズをせっせと拭かなければならないので、
水を良く吸い取るタオルなどが必須です。風景写真の極意は「待ちの忍耐」と「イマジネーション」、
そして僅かな変化を見逃さない集中力ではないでしょうか。
機材故障の話
先日、松島に取材で出掛けた折、
カメラマン人生で初めて2台同時にカメラのトラブルが発生しました。
まずCanon 5DMarkⅡにErr30がモニターに表示され撮影不能。
Canon40DはAFが故障。同行の編集者達の顔が一瞬蒼くなりましたが、
幸い予備機のNikonは何の問題もなく最後まで順調に働いてくれました。
プロとして何年かに一度の故障に備えたえず予備機材を携帯するのですが、
それにしてもデジタルカメラに移行してから故障の頻度が多くなり、
肩にかかるカメラバックが重たいことよ。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/4秒,絞りF16、ISO400。
使用機材
Canon 1Ds MarkⅡ、24~105ミリISレンズ(55ミリで使用)。
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家
ルリタテハと空巣老人2009.10.30
リコーGRデジタルカメラを構え、
とある神社境内でテリトリーを張るルリタテハに注視していた。
ふとルリタテハだけでは何かが足りないように思へ、
画に深みと味わいを与える背景には何が良いのかと思案した。
大袈裟な表現をお許し頂けるならば、
テリトリーを張るルリタテハには
なんだか哲学者の雰囲気が漂っているように思えてならないのだ・・・。
9/20付けの朝日新聞のコラムに
『漢語的不思議世界』(岩波書店)から引用した「空巣老人」について記事が出ていた。
一部抜粋「▼空き巣狙いの怪老人、ではない。
独り暮らしのお年寄りのことだという。
雛が育って飛び立てば、巣は空っぽになる。・・・」以下略。
当初この写真を公開する予定は全く無かったけれど、
「空巣老人」なる妙な響きに魅せられて、ルリタテハを公開することにした。
ルリタテハ(瑠璃立羽)
黒褐色の翅の表面には鮮やかな水色の帯模様がカタカナの「ノ」字のように入っているので見分けは簡単ですが、
しかし翅を閉じると枯れ葉や樹皮に似てとても見つけにくくなります。
飛翔スピードは高速で、♂は小高い岩の上や小枝などでテリトリーを張り、
近づく者にはご自慢の高速飛翔でもって奇襲攻撃を仕掛け、侵入者の追っ払いに精を出します。
コンパクトデジタルカメラの話
この時使った道具は「GRデジタルカメラ」です。
画作りの道具のひとつとしてコンパクトデジタルカメラを使うの一番の理由は
「持ち運びの利便性」と「深い被写界深度」。
GRはレンズ交換単焦点レンズ(広角28ミリ)が出来ないコンパクトデジタルカメラです。
少しだけこのカメラの歴史をお話しすると、1996年「プロのサブフィルムカメラ」として「GR1」が誕生。
2001年「GR 1v」が発売され、
当時は珍しい非球面レンズを2枚と広角レンズ搭載ながら
コンパクトカメラでは珍しディストーション(歪曲収差)が少なく、
写りの良いコンパクトカメラとして高評価を得ていました。
面白い事に2005年10月「GRデジタルカメラ」が発売されると、
逆に「GR 1v」の人気が再燃し、
中古市場では現在でも高値で取引される希なフイルム式コンパクトカメラとなっています。
言うまでもなくデジタルに変わっても
プロやハイアマチュアに高評価を得ていることには変わりありません。
ちなみに私はコンパクトで手に馴染むフィット感が心地よくフイルム式2台、
デジタル2台を所有しています。
この時の撮影技法
撮像素子(CCD)は1/1.8型サイズ(6.9×5.2mm)800万画素(最新GRⅢはCCDが1/1.7型1000万画素)です。
ちなみにフルサイズは36×24mm。
この小さな撮像素子に800万画素を詰め込むには多少無理があると思われますが、
撮像素子が小さければ被写界深度が深くなり、
広角28ミリレンズの「接写」では背景までボケの少ない写真を簡単に撮ることが出来るのです。
逆にフルサイズの撮像素子の場合その逆ということになります。
コンパクトカメラの隠された利点として、
公園などで撮影中デジタル一眼レフカメラを構えていると
「何かいるんですか?」などと肝心な場面でよく声をかけられ困ることが多いのですが、
コンパクトデジカメなら滅多に声をかけられないのです。
人に警戒感を与えないのも隠された撮影技法のひとつかもしれませんね。
カメラ設定
露出設定マニュアル、シャッタースピード1/125秒,絞りF8、ISO400、マクロに設定。
使用機材
リコーGRデジタル(28mm単焦点レンズ)
POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄
写真家