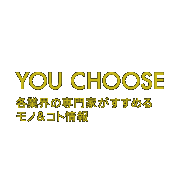世界的な時差はあるにせよ、ティーンエイジャーの無防備な、ナイーブなエネルギーが作りだした60年代の革命幻想も、70年代中ごろに入ると次第にゆるゆるの普通の日常の風景の中に埋没してゆきました。音楽においても、あの思い出したくもない「低能サタデーナイトフィーバー」と、「馬鹿スタジアムロック」という「消費者として十分に飼いならされたティーンエイジャー」ばっかり、という状況になってきました。
そんな時突然やってきたのが「PUNK」です。ニューヨークとロンドン両方からやってきたこの新しい波ですが、私はロンドンというかイギリスのほうに夢中になりました。1977年の初めのころと思いますが、Sex Pistolsのことを最初に知ったのは朝日新聞(と思う)の写真入りの記事でした。
「今ロンドンでパンクロックが人気。すべてに対して怒りをぶつけ、何も信じない若者たち。髪の毛を短く乱雑に切って、色を染め、Tシャツをぼろぼろにして、安全ピンをピアスにしている」みたいな内容だったと思います。それを読んだ時実はすごく嫌な感じがしたのを覚えています。「なんだよ、今更ストレートな怒りを表現したり、反体制の不良ぶったり、そんなことで何かが変わると思ってんの。馬鹿じゃん。」という屈折した感覚でした。
しばらくして、よく通っていたイギリスのトラディショナルフォークやプログレッシブロックを扱っていたレコード屋の隅に見たことのない変な、でもやけにカッコイイジャケットのレコードが置いてあって、それがSex Pistolsのこのアルバムでした。とにかく、見たことないデザイン、でも強烈な光を放っていて、あのいやな印象がありながら、結局買いました。そして家で聞いてみたら、もう何もかも全てが分かりました!って感じでした。不良がどうのこうのとか、ロックンロールの復権とか、全然筋違いの、本当に新しい、新しい人類が出現した、とでも言いたくなるような、すごい、かっこいい音でした。
直感的に感じたのは、まさにこの「新しさ」なんですが、その新しさとは「社会や歴史から切り離されている」スカスカした感じです。
その頃はこのことをうまく言えなかったんですが、今ならこう表現できるでしょう。
つまりロックが「反体制」だったのに対して、PUNKは「脱体制、脱社会」。もう反対すらしない。それも無効。社会の底が抜けた感じ。
「俺はほとんど空っぽ」「手に入れ方は知っているが、何がほしいのか分からない」という歌詞、にそのことがよく表れています。
この後、BUZZCOCKS,ADVERTS,WIREなどのPUNKから、80年代に入っての「NEW WAVE」に至る「脱社会的存在となった大量のティーンエイジャーが音楽、映画、文学、ファッションなどで猛威をふるう」、つまり今に至る時代が続いたという気がします。
SEX PISTOLSのジョニーロットンが「ロックは死んだ」と言ったのは有名ですが、それはこういうことなんだと思います。またジョンレノンが殺された時多くの人が「悲しい」「怒りを覚える」「時代が終わった」などの感傷的な言葉を口にする中、彼は顔をしかめて「何も変わんないさ」と言ったのが印象的でした。
POSTED BY:

HIKARU MACHIDA/町田光
NFL JAPAN 代表取締役社長 立命館大学客員教授 早稲田大学講師
1960年代後半の世界的バンドブームはなぜ起きたのか。
「黄金の60年代」などとよく言われようにロックやポップスだけでなく他の音楽、映画、演劇、美術、さらにはファッション、スポーツに至るまで、いわゆるユースカルチャーのほとんどがこの時代に生まれ、大衆化しています。
それは「Teenager」という存在が登場し、台頭したという現象とシンクロしています。
Teenagerとは何か。それは単に「10歳から20歳」という「年齢層」を指す言葉というよりももっと象徴的な意味を表しています。つまり「すでに子供ではないが、生産する側となることを猶予されている存在」とでもいうことができるのではないでしょうか。
1900年初頭では、もっとも公教育が進んでいたアメリカでさえハイスクールの進学率は8.4%、ヨーロッパのそれは3%以下でした。さらにその50年前にはアメリカの小学校の就学率が40%以下です。
つまりかつては子供の次はすぐに大人、つまり生産に従事する存在に直結していたのです。しかも7〜8歳のころにはすでに十分に「大人」、つまり「労働者」とみなされたのです。
それが社会が豊かになるに従い、人間と社会の発展には幼年期の「教育」が不可欠であり、子供たちに「教育を受ける権利」を与える、という認識が高まりました。
2回の世界大戦が終結し、その中で最も傷の浅かったアメリカでは、戦後のベビーブーマーが15歳に差し掛かる1960年ころにはすでに70%近くがハイスクールへ進学し、大学進学率も都市部を中心に大きく伸びていました。
彼ら「Teenager」は生産者となることを猶予されただけでなく、高度成長社会の新たな「消費者」の役割が与えられます。
そしてこの状況は数年の差を持ちながら世界のほかの国や地域でも起こってゆくことになります。
つまり今では当たり前の「Teenage」という概念、そして「Teenager」という存在はせいぜいこの50年間くらいの間に誕生したものなのです。そしてその最初の「Teenager」たちは、世界が消費社会に突入しようとしていた時代の流れとその絶対的な「数量」によって、社社会全体を巻き込みひっくり返すほどのエネルギーを持っていたのです。
そのエネルギーの中には、何のルールもなくそれこそなんでもありで、明ー暗、体制ー反体制、美ー醜、創るー壊す、などが入り乱れそれがそのまま、音楽、映画、演劇、美術、スポーツ、政治、経済の中で繰り広げられました。
面白くなるわけです。
しかし同時にこれらが「生産しない者たち」、つまり「お小遣い」の世界での出来事だった、という本質的なひ弱さ、があったことも忘れてはならないでしょう。でも、だから純粋でもあったのです。
それに対して現在の「Teenager」はあらかじめ「若者」というカテゴリーが与えられ、重要なマーケットとして研究され、大切な消費者として囲われ、整地され去勢されてしまいました。そのことを「情けない」などといっても仕方ないでしょう。あの60年代のエネルギーも自然発生的であったこと、故に無自覚であったため、結局あれだけのものを生み出しながら、ほとんどの人々にとって「あの頃はよかった」というただの思い出です。前も言いましたが「あの頃はよかった」という姿勢ほど気持ちの悪いものはありません。
あの頃、が素晴らしかったのはなぜか、なぜそれは消えたのか、今何がなくて、何があるのか、それを考えることが、あの面白さをこれからも作り出せるのだと思います。それはまず個人の営みとして、その生活や仕事の中での実践です。
POSTED BY:

HIKARU MACHIDA/町田光
NFL JAPAN 代表取締役社長 立命館大学客員教授 早稲田大学講師